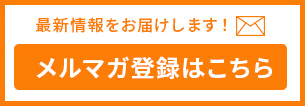電話対応を削減・業務効率化する方法や事例・おすすめツールを解説
更新日:2025.12.2

「電話の対応に追われ、本来の業務が進まない…」
「同じような内容の問い合わせが多く、対応に時間を取られてしまう…」
会社で電話対応を行う担当者様のなかには、こんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
日々の電話対応は、企業のビジネスを支える重要な業務ですが、その一方で多くの時間と労力が費やされ、生産性を低下させる一因になっているケースも少なくありません。
そこで本記事では、電話対応を削減・効率化する方法やおすすめのITツール、成功事例をわかりやすく解説します。
目次
なぜ「電話対応」は非効率になりやすいのか?
そもそも、なぜ電話対応は非効率な状態に陥りやすいのでしょうか。その背景を示す、企業側の体制や顧客の行動に関する客観的なデータがあります。
楽天コミュニケーションズが2023年に行った調査によると、中小企業の6割以上が「電話対応に課題がある」と回答しています。具体的には「即答できず折り返しが多い」や「対応する人がいない」といった声が多く挙がりました。
これは、多くの企業で電話対応を専任担当や特定の窓口に集約できておらず、従業員が本来の業務の合間に対応している実態を浮き彫りにしています。

電話対応を削減・効率化すべき7つの理由
電話対応の非効率性を放置すると、単に「忙しい」という問題だけでは済まされません。ここでは、電話対応を削減・効率化すべき7つの理由について解説します。
1. 業務の中断による生産性の低下

電話対応の最も大きな問題点は、本来の業務を強制的に中断させてしまうことです。集中して企画書を作成している時や、重要なデータ入力をしている最中に電話が鳴れば、一度思考を止めなければなりません。
カリフォルニア大学アーバイン校の調査によると「人間の脳は一度中断した作業に再び集中するまでに時間を要し、複雑なタスクほど回復に時間がかかる」とのデータが示されています。
したがって、頻繁な電話対応による業務の中断は、従業員一人ひとりの生産性を著しく低下させる要因となります。
2. 受電漏れによる売上機会の損失

営業時間外や繁忙期、担当者が他の対応で手を離せない状況では、どうしても受電漏れ(電話の取りこぼし)が発生してしまいます。新規顧客からの問い合わせはもちろん、既存顧客からの重要な相談などを逃してしまうと、そのまま売上機会の損失に直結します。
とくに対応を急ぐ顧客ほど、一度電話がつながらないだけで競合他社に流れてしまう可能性も少なくありません。
株式会社PR TIMESが行った問い合わせ対応に関するアンケート調査によると、サポート体制や応対品質などを理由に、問い合わせを諦めた人の割合は4割を超えていると報告されています。
3. 属人化による対応遅延と信頼低下

「商品・サービスに詳しいAさんしか対応できない」といった業務の属人化は、電話対応の大きな課題です。特定の担当者しか対応できない状況では、その担当者が不在だったり他の電話で手が離せなかったりすると、顧客対応がストップしてしまいます。
対応の迅速性を欠いて顧客を待たせしてしまうケースが発生し、とくに緊急性の高い問い合わせにおいては、信頼を大きく損なうリスクがあります。対応内容が共有されず属人化していると、他の担当者が状況を把握できず適切な対応が取れないため、顧客の不安や不満を助長する結果となりかねません。
さらに、対応業務ノウハウが個人に留まり社内に知識として蓄積されないことで、同様の対応を他のスタッフが行えず、業務の標準化や改善が進まなくなります。
4. 対応の遅れによる顧客満足度の低下

「担当者から折り返します」と言ったもののまだ返信できていない、あるいは質問のたびに「確認しますのでお待ちください」と長時間待たせてしまう。このようなレスポンスの遅れは、顧客満足度を損ないます。
また、担当者によって対応品質にばらつきが生じると、顧客は不信感を抱いてしまうでしょう。
顧客が求めているのは、迅速かつ的確な一貫性のある回答です。レスポンスの遅れや回答内容の不一致は「この会社は信用できない」というネガティブな印象を与えてしまい、競合他社への乗り換えや契約の打ち切りといった事態を招きかねません。
株式会社モビルスの調査によると、「問い合わせ対応に不満で購入・利用をやめた経験あり」という回答が50%を超えており、電話対応の品質が直接的に顧客離れにつながることが明らかになっています。
5. 従業員のストレス増加やモチベーションの低下

ひっきりなしに鳴る電話や、同じような質問ばかりに対応せざるを得ない状況は、従業員にとって大きな精神的ストレスとなります。くわえて本来集中すべき業務が進まないことへの焦りも、ストレスをさらに増大させるでしょう。
このような状況が続けば、従業員の仕事に対するモチベーションは低下し、最悪の場合、休職や離職につながるリスクもあります。こうした従業員満足度の低下は個人の問題にとどまらず、企業全体のパフォーマンスやサービスの質にも悪影響を及ぼします。
6. 電話が苦手な若年層が増えていることへの対応
近年、電話でのコミュニケーションを苦手とする若年層が増えています。SNSやチャットツールなどのテキストコミュニケーションに慣れ親しんだ若い世代にとって、電話は心理的なハードルが高いと感じられるためです。
また、電話対応を行う従業員も「すぐに応答しなければならない」や「言葉を選ぶ余裕がない」といったプレッシャーを感じやすく、精神的な負担となっているケースは少なくありません。ほかにも「やりとりが文字に残らない」という電話特有の非効率性も、苦手意識を助長する要因のひとつです。
今後はこうした電話を苦手とする層が増えていくことから、電話メインの問い合わせ対応のままでは、将来的に顧客接点や従業員の志気を失うリスクがあります。

7. 増員による人件費の増加

電話対応の量が増え続け、現在の従業員だけでは対応しきれなくなった場合、もっとも直接的な解決策は「人員を増やす」ことでしょう。
しかし、深刻な人手不足が続く現代において、そもそも新たな人材を確保すること自体が困難です。多額の採用コストをかけても、必ずしも求める人材が見つかるとは限りません。
仮に人員を増やせたとしても根本的な業務プロセスが変わらなければ、いずれまた同じように対応業務が逼迫する不安は解消されません。
電話対応を効率化する5つの方法
ここでは、電話対応を効率化する代表的な5つの方法を紹介します。それぞれの方法で得られる主な効果もあわせて解説します。
1. 電話対応マニュアルによる対応品質の統一

「電話担当者によって対応品質にばらつきがある」という課題は、電話対応マニュアルを作成することで解決できます。よくある質問への回答集や担当部署へのスムーズな取り次ぎ方法、イレギュラー発生時の対応策などを標準化することで、誰が応対しても一定の品質を保てます。
電話対応業務の効率化や属人化を防ぐだけでなく、新人教育用の資料としても活用できるため、教育コストの削減や育成スピードの向上にも寄与します。
2. FAQページ設置による自己解決率の向上

「よくある質問と回答」をまとめたFAQページをWebサイト上に設置することも効果的です。多くの顧客は、問い合わせる前に「まず自分で解決しよう」と試みます。その際に充実したFAQページがあれば、顧客は電話することなく疑問を即座に解消できるため、問い合わせ件数そのものを減らせます。
効果的に運用するためには、顧客が求める情報を的確に反映し、FAQページを継続的に見直すことが大切です。
3. 電話以外の問い合わせ窓口の設置

電話による問い合わせ対応は業務負担が大きく、属人化や対応遅延の原因にもなりがちです。そこで予約の確認や変更など、電話でなくても対応可能な場合には、Webフォームのようなテキストベースの窓口を設けることで、業務の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。
電話以外の問い合わせ窓口を設けることは、業務効率化だけでなく、顧客との接点を維持・強化するためにも有効な手段です。こうした対応チャネルの多様化は、カスタマーサービスの向上や新規売上げの獲得にも役立ちます。
4. 電話代行サービスの利用

「社内のリソースだけでは対応しきれない」や「繁忙期だけ外部委託したい」という場合には、電話代行サービスの利用も選択肢のひとつです。外部委託することで、従業員は電話対応に費やしていた時間を削減し、本来の業務に集中できる環境が整います。
代行先のオペレーターが一次対応を行うことで受電漏れを防ぎ、応対内容はメールやチャット、SMSなどで随時報告してくれます。また、時間外窓口や緊急連絡先としても利用可能なサービスもあり、対応漏れによる機会損失やクレームのリスクを軽減できます。
5. 電話対応を効率化するITツールの導入

近年、電話対応を削減・効率化するITツールが多数登場しています。なかでも代表的なものがAIチャットボットや自動音声応答システム(IVR)、FAQシステム、対応履歴管理ツールです。
これらのITツールを活用すれば、人に頼らない対応体制を整えられるほか、業務の安定化や情報管理の効率化にもつながります。
【比較表あり】おすすめの電話対応効率化ツール8選
電話対応を効率化するツールは、用途に応じてさまざまなサービスが登場しています。ここでは、代表的な4種類のツールごとにおすすめのサービスを紹介します。
AIチャットボット
AIチャットボットとは、ユーザーからの質問や問い合わせに対してAI(人工知能)が自動で回答するシステムです。Webサイト上に設置し、訪問者からの質問に自動で24時間365日対応します。
従来のチャットボットでは、想定される質問の洗い出しや回答シナリオを事前に作成する必要がありましたが、生成AIを連携させることで手間なく導入できるようになりました。電話対応の削減に加え、営業時間外の機会損失の防止にも有効です。
DSチャットボット

公式サイト:https://dschatbot.ai/(株式会社ディーエスブランド)
DSチャットボットは、WebサイトURLやPDFファイルを読み取らせるだけで、すぐに導入できるAIチャットボットです。社外からの問い合わせ対応はもちろん、社内ヘルプデスクや採用活動(多言語オプション)まで幅広く利用できます。
対応履歴の蓄積・分析に加え、AI学習や回答評価、レポート出力などチャットボット運用に必要な機能が揃っています。ユーザーがサイト内でどのページを閲覧したかの情報も履歴として蓄積するので、マーケティング活動の改善にも効果的です。
導入から運用まで支援するサポート体制(電話応答率98%以上)も充実しており、初めてAIチャットボットを導入する企業に最適です。
KUZEN(クウゼン)

公式サイト:https://kuzen.io/support(株式会社クウゼン)
KUZENは、LINE・Slack・Teamsなど30以上の外部サービスとシームレスに連携できるAIチャットボットです。ノーコードで直感的に会話フローを設計でき、業界別テンプレートも豊富に用意されているため、スピーディに運用を始められます。
導入実績は600社以上で、自治体や製造業、金融業界など幅広い業種で利用されており、安心感のあるサービスとして支持されています。
自動音声応答システム(IVR)
自動音声応答システム(IVR)とは、通話時の操作に応じてあらかじめ用意した音声で自動応答するシステムです。たとえば「契約に関するお問い合わせは1番を、納期に関するお問い合わせは2番を…」のような音声ガイダンスに沿って進行するものです。
問い合わせ内容に応じて適切な部署や担当者に直接電話をつなぐことで取り次ぎの手間を省き、顧客を待たせる時間を短縮します。
IVRy(アイブリー)

公式サイト:https://ivry.jp/(株式会社IVRy)
IVRyは、コストパフォーマンスに優れるクラウド型の自動音声応答サービスです。
「〇〇の方は1番を…」といった音声ガイダンスの分岐設定を、パソコンやスマートフォンからいつでも簡単に作成・変更できます。ほかにもSMS返送や受電通知、AIによるガイダンス読み上げなどの機能を備えており、企業規模を問わず手軽に電話業務を自動化できる点が魅力です。
自動受付IVR

公式サイト:https://www.dhk-net.co.jp/service/autoreception-system/(株式会社電話放送局)
自動受付IVRは、夜間や休日などの営業時間外の電話受付の自動化に特化した自動音声応答サービスです。導入実績500社以上を誇り、年間4,000万件以上の処理件数を実現しています。
企業の要望に応じた柔軟なカスタマイズが可能で、既存の社内システムとの連携にも対応しています。24時間365日の注文受付や、大規模なキャンペーンの応募受付など、特定の用途に合わせた高度な自動化を実現したい場合に最適です。
FAQシステム
FAQシステムとは、単にFAQページを作成するだけでなく、高度な検索機能や分析機能を備えた専門ツールです。単に質問と回答を羅列しただけのWebページとは異なり、FAQシステムは「ユーザーが求めている答えにいかに早く、簡単に解決できるか」を追求しています。
たとえば、顧客が入力したキーワードから適切な回答を提案したり、どの質問がよく検索されているかを分析したりする機能を備えています。ユーザーの自己解決を促進して、問い合わせ件数の削減と顧客満足度の向上を同時に実現します。
PKSHA FAQ(パークシャエフエーキュー)

公式サイト:https://aisaas.pkshatech.com/faq/(株式会社 PKSHA Technology)
PKSHA FAQは導入実績1,500サイト以上を誇り、あらゆる業種に選ばれているFAQシステムです。ユーザーが入力した曖昧な言葉や話し言葉でも、AIが意図を汲み取って的確な回答候補を提案します。
「どの質問がよく見られているか」や「どの質問が解決できていないか」などをAIが分析し、FAQシステムの肝ともいえる継続的な改善をサポートします。また、自由度の高いデザインでカスタマイズもできるので、Webサイトのブランドイメージに調和したFAQページを構築できます。
sAI Search(サイサーチ)

公式サイト:https://saichat.jp/saisearch/(株式会社サイシード)
sAI Searchは、 ユーザーが検索せずに回答を見つけだせる独自AIを搭載したFAQシステムです。AIの提示するタグの中から、ユーザーが疑問に思っていることに関連するタグを直感的に選択していくだけでFAQが絞られていき、目的の回答にたどり着けます。
導入もかんたんでFAQデータをアップロードするだけで運用を始められるので、Webサイトの情報量が多い企業でも手軽に検索性を向上できます。
対応履歴管理ツール
対応履歴管理ツールとは、顧客や取引先からの問い合わせ内容を記録して一元管理するシステムです。電話・メールなどの対応履歴を記録して、対応中・完了などの状態を管理します。「誰が・いつ・どんな対応をしたか」を記録・管理できるので、抜け漏れや二重対応の防止に加え、担当者間の情報共有も円滑になります。
企業規模を問わず工夫次第でさまざまな活用ができるため、業務のDX化に初めて取り組む際のおすすめツールです。
おりこうブログDX

公式サイト:https://oricoh-blog.com/dx/(株式会社ディーエスブランド)
おりこうブログDXは、Webサイト作成ツール(CMS)に、サイボウズ社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」を連携させたWebソリューションです。
予約の確認・変更などの電話でなくても対応可能なケースにおいて、kintoneと連携したWebフォームから申し込んでもらうことで、利用者自身がいつでも情報の照合・変更が行えます。Webフォームからの情報をkintoneに自動保存して管理できるため、情報を転記する手間がなくなり、業務負担の軽減につながります。
そして、おりこうブログDXの最大の強みは、kintone内に蓄積したデータをWeb上に自動で反映・公開できる点です 。ID・パスワードで保護された限定公開ページに情報を掲載すれば、kintoneのライセンスを持たない従業員や外部関係者ともリアルタイムに共有できます。共有したいチーム全員分のライセンスコストをかけることなく、kintoneを中心とした対応履歴管理体制を低コストで構築したい企業に適しています。
導入から運用まで支援するサポート体制(電話応答率98%以上)に加えて、kintone連携に関するサポート窓口も設置しており、ITに詳しくなくても安心して運用できます。
Customa!(カスタマ)

公式サイト:https://customa.jp/(株式会社アイバス)
Customa!は、顧客管理だけでなく営業支援や見積書の発行など、営業活動全体を効率化するための多機能ツールです。中小企業の現場での使いやすさを重視して設計されており、専門的なIT知識がなくても簡単に導入・運用できます。また、ユーザー数無制限で利用したデータ容量制での課金なので、利用量に応じて無駄なく使える点が特徴です。
電話対応だけでなく営業支援も効率化したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。
電話対応削減・効率化のITツール比較表(2026年2月時点)
ツール種類 | サービス名 | 特徴・強み | 無料体験・プランの有無 | サポート体制 | 価格 |
AIチャットボット |
| 自社サイトに設置できる無料トライアルあり | 導入・運用支援 電話・メールサポート | 月額5,500円~ | |
| 記載なし | 導入・運用支援(プランによる) | 要問い合せ 自動音声応答システム(IVR) | ||
自動音声応答システム(IVR) |
| 無料プランもあり | メールサポート | 要問い合わせ 月額2,980円〜 | |
| 無料デモあり | 電話・メールサポート | 初期費用300,000円~ 月額150,000円~ | ||
FAQシステム |
| 記載なし | メールサポート | 要問い合わせ | |
| 記載なし | 導入・運用支援(プランによる) | 要問い合わせ | ||
対応履歴管理ツール |
| 無料トライアルあり | 導入・運用支援 電話・メールサポート | 要問い合わせ | |
| 記載なし | メール・オンラインサポート | 月額9,980円〜 |
電話対応の削減・効率化に関するよくある質問
電話対応の削減・効率化に関する、よくある質問を以下にまとめました。
Q. 電話対応を効率化すると顧客満足度が下がるのでは?
むしろ顧客満足度の向上につながるケースが多いです。
AIチャットボットやFAQを設置すれば、顧客は待たされることなく疑問をすぐに解決できます。複雑な相談に対しては有人対応の窓口を残しておくなど、柔軟な窓口体制を検討しておきましょう。
Q. AIチャットボットとは何ですか?
AIチャットボットとは、ユーザーからの質問や問い合わせに対してAI(人工知能)が自動で回答するシステムです。Webサイトに導入することで、人手をかけずに24時間365日対応できます。
Q. 少人数の企業でも電話対応を効率化するITツールの導入は有効ですか?
はい、非常に有効です。
少人数の企業ほど、一人の従業員が多くの業務を兼任しています。電話対応に時間を取られることによる生産性の低下は、大企業以上に深刻な問題です。そのため、少人数の企業でもITツールの導入は、限られた人員での業務負荷を軽減する有効な手段となります。
Q. AIチャットボットでは対応できない複雑な問い合わせはどうなりますか?
多くのAIチャットボットには、解決できない問い合わせがあった場合、問い合わせフォームなどの窓口へスムーズに誘導する機能が備わっています。
AIチャットボットが一次対応を行い、複雑な案件のみを人が引き継ぐことで、効率的かつ質の高い顧客対応を実現できます。
Q. ITツールを導入する際の選定基準や比較ポイントはありますか?
まずは「自社の課題は何か」を明確にすることが重要です。
「問い合わせ件数そのものを減らしたい」ならチャットボットやFAQシステム、「取り次ぎの手間をなくしたい」ならIVRが適しています。
導入したいツールが決まったら、操作のしやすさやサポート体制、コストなどを比較検討しましょう。無料トライアルなどを活用し、実際に試してみるのがおすすめです。
Q. 電話対応効率化の成果をどうやって測定すればいいですか?
おもな指標は「問い合わせ件数の変化」「電話の応答率」「平均対応時間」「顧客満足度アンケートの結果」などです。ツール導入前と導入後でこれらの数値を比較することで、効果を客観的に測定できます。多くのツールには分析機能が搭載されており、これらのデータを簡単に収集できます。
電話対応の削減・業務効率化は生産性向上への第一歩
本記事では、電話対応を削減するための具体的な方法や用途ごとに適したITツール紹介、成功事例などを取り上げました。
電話対応の効率化は、単なるコスト削減や業務負担の軽減にとどまりません。削減した時間を付加価値の高い業務に充てることで従業員のモチベーションを高め、ひいては顧客満足度の向上や売上アップにもつながります。これは、人手不足が深刻化する今後の日本社会において、企業が持続的に成長していくための重要な第一歩です。
「ITツールは難しそう」という固定概念を一度リセットし、自社の課題解決に最適な方法を探してみてはいかがでしょうか。今回ご紹介したツールの中には、無料トライアルが可能なものもあります。まずは気軽に試してみることから始めてみましょう。
初めてのAIチャットボット導入なら「DSチャットボット」
弊社ディーエスブランドが提供する「DSチャットボット」は、WebサイトのURLやPDFを読み取らせるだけで簡単に設置できる点や、充実したサポート体制に強みを持つAIチャットボットです。生成AI(ChatGPT連携)による自然な対話と、顧客ニーズの分析に役立つレポート生成機能で、業務効率化と同時にマーケティング活動の改善にも貢献します。
また、サービスの設定方法から活用方針などの運用サポートはもちろん、いつでもつながる電話サポートもあるため、ITスキルに不安がある企業や初めてAIチャットボットを導入する企業でも安心です。
「AIチャットボットを導入したいが、自社に最適なのはどれだろう?」と検討中の方は、まずはDSチャットボットの資料をご覧ください。
この記事を書いた人

高島 耕
株式会社ディーエスブランド Webマーケター
ディーエスブランド入社後、メールマーケティングやセミナー運営、社内業務のDX化に携わる。現在はメタバースや生成AIなどの、先端技術分野のライティングを担当。