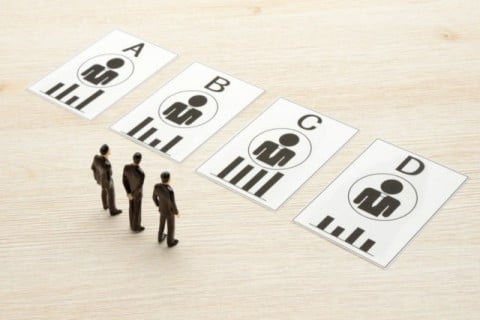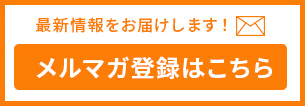チャットボットとは? 意味や仕組み・メリットを簡単にわかりやすく解説
更新日:2026.2.5

- 「最近、チャットボットという言葉をときどき目にするけど、どんなものかは詳しく知らない…」
- 「チャットボットを導入するメリットや効果がわからない」
こんな疑問やお悩みはありませんか?
近年になってチャットボットのビジネス利用は急速に進んでいますが、いまいちチャットボットの意味やメリットがわからないという方も多いと思います。
今回はチャットボットの意味やメリット、仕組み・使い方を簡単にわかりやすく解説します。自社の業務効率化や顧客満足度向上、売上げアップに興味がある方はぜひご覧ください。
目次
[非表示]
- チャットボットとは?
- チャットボットの仕組み・種類
- シナリオ型(ルールベース型)のチャットボットとは?
- AI型のチャットボット(AIチャットボット)とは?
- チャットボットのメリット
- メリット1.お問い合わせ対応業務の効率化
- メリット2.24時間・365日、顧客対応できるようになる
- メリット3.同時に多数のお問い合わせに対応できる
- メリット4.社員ごとの顧客対応のクオリティのバラつきに悩まされない
- メリット5.新規お問い合わせやコンバージョンの獲得率向上
- メリット6.顧客が質問するハードルが下がる
- メリット7.会話データ蓄積による顧客理解度の明確化、マーケティング・経営への活用
- メリット8.採用活動も効率化 求職者の隠れたニーズも引き出せる
- メリット9.業務の属人化の防止と、ナレッジの蓄積
- メリット10.外国語での対応を大幅に効率化し、販路拡大や人材獲得にもつながる
- メリット11.昨今増加している電話が苦手な従業員・顧客の負担を減らせる
- チャットボットの用途・使い方
- 社外向けのチャットボットの使い方
- 社内向けのチャットボットの使い方
- おすすめのチャットボット一覧
- DSチャットボット 初心者でも使いやすいAIチャットボット
- AIチャットボットさくらさん 大企業や自治体に多数の導入実績
- ChatPlus 導入数2万社以上の低価格で使えるチャットボット
- sinclo 簡単で分かりやすいチャットボット型Web接客ツール
- KARAKURI chatbot カスタマーサポートに特化したチャットボット
- HiTTO バックオフィス部門の業務効率化に特化したチャットボット
- チャットボットについてのよくある質問
- 今後の人手不足・グローバル化に対応するには、チャットボットの活用が効果的!
- あわせて読みたい記事
チャットボットとは?
チャットボットとはユーザーからの質問に自動で返答してくれるプログラムのこと
チャットボット(Chatbot)とは、チャット(会話)とボット(ロボット)を組み合わせた言葉で、ユーザーからの質問に自動で返答してくれるプログラム(自動会話プログラム)のことを指します。
チャットボットをビジネスに利用することで、これまで人間が対応するしかなかったお問い合わせ対応やカスタマーサポートを自動化できます。
すでにLINEやFacebookでもチャットボットが活用されていますし、企業のホームページの右下に「何かお困りごとはありませんか?」などのメッセージとともにチャットボットが表示されているのを目にした方も多いかもしれません。
また、AppleのSiriやGoogleアシスタントなど音声で会話するプログラムも、広い意味でのチャットボットの一種です。
チャットボットをビジネスに利用することで、これまで人間が対応するしかなかったお問い合わせ対応やカスタマーサポートを自動化できます。
すでにLINEやFacebookでもチャットボットが活用されていますし、企業のホームページの右下に「何かお困りごとはありませんか?」などのメッセージとともにチャットボットが表示されているのを目にした方も多いかもしれません。
また、AppleのSiriやGoogleアシスタントなど音声で会話するプログラムも、広い意味でのチャットボットの一種です。

近年になってチャットボットがビジネスで注目されはじめた理由とは

チャットボットの歴史は意外に古く、1960年代にアメリカで開発されたELIZA(イライザ)がその源流だとされています。
ですが、当時の自動会話プログラムは質問に対して定型的な返答しかできず応用がきかなかったため、近年に至るまでビジネスで広く利用されることはありませんでした。
ですが、当時の自動会話プログラムは質問に対して定型的な返答しかできず応用がきかなかったため、近年に至るまでビジネスで広く利用されることはありませんでした。
しかし、2010年代以降にAI(人工知能)の性能が格段に向上することでチャットボットの性能も飛躍的にアップし、柔軟性のある回答ができるようになりました。
また、ビッグデータの活用によりAIは会話の学習を急ピッチで続けており、質問の意図を読み取る自然言語処理の能力も日々成長を重ねています。
以上のような理由から、近年になってチャットボットがビジネス分野でも急速に普及するようになったのです。
また、ビッグデータの活用によりAIは会話の学習を急ピッチで続けており、質問の意図を読み取る自然言語処理の能力も日々成長を重ねています。
以上のような理由から、近年になってチャットボットがビジネス分野でも急速に普及するようになったのです。
チャットボットの仕組み・種類
チャットボットの仕組みには、大別してシナリオ型(ルールベース型)とAI型の2種類が存在します。
それぞれどうちがうのか、紹介していきます。
シナリオ型(ルールベース型)のチャットボットとは?
管理者が事前に設定したQ&Aシナリオをもとに対応する形式が、シナリオ型のチャットボット
シナリオ型(ルールベース型)とは、管理者があらかじめ設定しておいたQ&Aシナリオをもとに、ユーザーに対応する形式のチャットボットのことです。
たとえば、以下のようなQ&A(質問と回答)のシナリオをあらかじめ設定しておくことで、ユーザーからの質問に自動回答できます。
【シナリオ型チャットボットのQ&Aシナリオの例】
Q:「リフォームやリノベーションにかかる期間はどれくらいですか?」
A:「一般的には1~2ヶ月程度ですが、プランによって異なります。詳しくは無料相談にお問い合わせください」
また、以下のような質問と回答が枝分かれしていくタイプも、典型的なシナリオ型チャットボットです。
Q1.新築とリフォームのどちらに興味がありますか?
A 新築 Bリフォーム
→ユーザーがAを選択
Q2.和風住宅と洋風住宅ではどちらに興味がありますか?
…以上のように、回答した選択肢に応じてパターンが枝分かれしていく。
たとえば、以下のようなQ&A(質問と回答)のシナリオをあらかじめ設定しておくことで、ユーザーからの質問に自動回答できます。
【シナリオ型チャットボットのQ&Aシナリオの例】
Q:「リフォームやリノベーションにかかる期間はどれくらいですか?」
A:「一般的には1~2ヶ月程度ですが、プランによって異なります。詳しくは無料相談にお問い合わせください」
また、以下のような質問と回答が枝分かれしていくタイプも、典型的なシナリオ型チャットボットです。
Q1.新築とリフォームのどちらに興味がありますか?
A 新築 Bリフォーム
→ユーザーがAを選択
Q2.和風住宅と洋風住宅ではどちらに興味がありますか?
…以上のように、回答した選択肢に応じてパターンが枝分かれしていく。
シナリオ型チャットボットのメリット
シナリオ型のチャットボットは、あらかじめ設定されている回答しか返さないため、正確な情報を伝えたい場合や、定型的な質問しか来ないシチュエーションで優れています。
また、仕組みが単純なので次にAI型のチャットボットと比較して、利用料金・コストが安価なのもメリットです。
シナリオ型チャットボットのデメリット
シナリオ型チャットボットの最大のデメリットが、Q&Aシナリオづくりの難易度の高さや大変さです。
実際、弊社でも自分たちの製品(おりこうブログ)についてチャットボットを作成したことがありますが、Q&Aのシナリオ作りの負担は予想以上に大きいものでした。
まず顧客に対する理解度が高くないと、どんな質問が来るのかわからないので、Q(質問)のシナリオを作れません。
また、Q(質問)に対する適切な回答(A)を用意するにも、深い商品・サービスに関する知識が必要になります。
さらに、Q&Aをわかりやすい文章で構成する、言語化の技術も不可欠です。
以上のように、チャットボットのQ&Aのシナリオづくりには以下の3つのスキルが必須になるので、難易度が高いですし負担も大きいのです。
【チャットボットのQ&Aシナリオづくりに必要なスキル】
- 高い顧客理解度・接客経験
- 商品・サービスに関する深い知識
- わかりやすい文章を書く言語化能力
AI型のチャットボット(AIチャットボット)とは?

AI型のチャットボットは、登録されたデータをAIが学習し、ユーザーからの質問に対して自動的に回答を作成します。
昨今は、ChatGPTなどに代表される生成AIの技術を活用したチャットボットが増えており、自然で人間らしい回答が可能になっています。
参考ページ:生成AI(ジェネレーティブAI)とは? 種類や使い方、活用例を解説
※なお、生成AIを使った業務効率化に興味のある方は、無料の資料を用意しておりますので、ぜひ以下からお気軽にダウンロードしてみてください。
昨今は、ChatGPTなどに代表される生成AIの技術を活用したチャットボットが増えており、自然で人間らしい回答が可能になっています。
参考ページ:生成AI(ジェネレーティブAI)とは? 種類や使い方、活用例を解説
※なお、生成AIを使った業務効率化に興味のある方は、無料の資料を用意しておりますので、ぜひ以下からお気軽にダウンロードしてみてください。
AIチャットボットのメリット

AIチャットボットの最大のメリットが、自分たちでゼロからQ&Aシナリオを組み立てる手間がいらないことです。
AIチャットボットなら、Webサイト内の情報やPDFの書類などを読み取らせるだけで、自動的にAIが学習を進めてくれるため、労力がかかりません。
そのため少ない時間で、手軽にチャットボットを導入できます。
また、英語・中国語・韓国語…といった日本語以外の問い合わせにも対応しやすいのも、AIチャットボットならではの魅力です。
多言語対応機能を備えたAIチャットボットであれば、たとえば英語で質問が来た場合には、自動的に英語で回答してくれます。
そのため、外国語でのお問い合わせ対応にかかる手間・時間を大幅に削減できます。
※なお、弊社の自動接客ツール・DSチャットボットも、AIチャットボットの機能を備えています。
Webサイトや、アップロードしたPDF書類の情報をもとに、AIが自動的に学習を進めるので、Q&Aシナリオ作成の手間は不要です。
また、多言語対応機能もありますので、海外の顧客からの対応や、訪日外国人・在留外国人のお客様からの問い合わせにも簡単に対処できます。
興味のある方は、ぜひ以下から詳細をご覧ください。
AIチャットボットのデメリット
生成AIを使用する関係で、AIチャットボットはシナリオ型チャットボットと比較してコストが高くなる傾向にあります。
また、回答を生成AIに任せるので、毎回100%正確な情報を回答してくれるわけではない点についても、留意しておかなければなりません。
また、回答を生成AIに任せるので、毎回100%正確な情報を回答してくれるわけではない点についても、留意しておかなければなりません。
チャットボットのメリット
チャットボットの主なメリットは以下の通りです。
【チャットボットのメリット】
- お問い合わせ対応業務の効率化
- 24時間・365日、顧客対応できるようになる
- 同時に多数のお問い合わせに対応できる
- 社員ごとの顧客対応のクオリティのバラつきに悩まされない
- 新規お問い合わせやコンバージョンの獲得率向上
- 顧客が質問するハードルが下がる
- 会話データ蓄積による顧客理解度の明確化、マーケティング・経営への活用
- 採用活動も効率化 求職者の隠れたニーズも引き出せる
- 業務の属人化の防止と、ナレッジの蓄積
- 外国語での対応を大幅に効率化し、販路拡大や人材獲得にもつながる
- 昨今増加している電話が苦手な従業員・顧客の負担を減らせる
それぞれ具体的に紹介していきます。
メリット1.お問い合わせ対応業務の効率化

【会社では電話対応に1年あたり120万円~400万円程度のコストがかかっている】
これまで顧客からの電話お問い合わせ対応に、企業は膨大な時間とコストを費やしてきました。
中小企業において、会社全体で1日あたりの電話対応にかけている時間を仮に2時間だとします。
これまで顧客からの電話お問い合わせ対応に、企業は膨大な時間とコストを費やしてきました。
中小企業において、会社全体で1日あたりの電話対応にかけている時間を仮に2時間だとします。
※純粋に電話に受けている時間だけでなく、質問に関する情報をリサーチする時間や折り返し電話をする時間も含めます。また、社内の電話受付のみではなく、社外に出ている営業社員が商品・サービスについての単純な質問を電話で受けている時間などもカウントします。
すると1ヶ月あたりの営業日(20日)×12ヶ月で、2時間×20日×12ヶ月となり1年あたり480時間を電話対応に費やしていることになります。
社員1人を1時間働かせるコスト(時給だけでなく、賞与・社会保険負担費・交通費などの費用も含む)が2500円だとすると、480時間×2500円で合計120万円ものコストを電話対応に毎年支払っていることになります。
中小企業にとって、これは決して軽くないコストです。
また、会社全体における1日あたりの電話対応が2時間というのはかなり少なめの数字なので、電話が多くかかってくる中小企業では、300万~400万円程度にまで電話対応にかかるコストは膨れ上がるでしょう。
また、会社全体における1日あたりの電話対応が2時間というのはかなり少なめの数字なので、電話が多くかかってくる中小企業では、300万~400万円程度にまで電話対応にかかるコストは膨れ上がるでしょう。
さらに中小企業では電話対応専任の社員が設けられていないことも多く、他の業務と兼任していることが多いです。
そのため、顧客からの電話対応をしている間に本来の業務が停滞してしまい、結局残業で処理することを余儀なくされている…という方もいらっしゃるでしょう。
そのため、顧客からの電話対応をしている間に本来の業務が停滞してしまい、結局残業で処理することを余儀なくされている…という方もいらっしゃるでしょう。
【チャットボット導入で業務負担とコストを大幅に削減!】
チャットボット導入により、簡単な質問については顧客が自己解決してくれるようになるので、お問い合わせ対応の業務負担が軽減されます。
これにより、社員の残業時間が短縮され、会社の働き方改革にもつながります。
また、電話対応で業務が寸断されることが少なくなり、人間でしか対応できない複雑なお問い合わせやよりコアな業務に社員が集中できます。
また、電話対応で業務が寸断されることが少なくなり、人間でしか対応できない複雑なお問い合わせやよりコアな業務に社員が集中できます。
仕事のクオリティ自体もアップするでしょう。
会社側にとっても、働きやすい職場になって社員の士気が上がるのは望ましいことです。
会社側にとっても、働きやすい職場になって社員の士気が上がるのは望ましいことです。
さらに社員の離職率低下も期待でき、採用コストの節約にもなります。
メリット2.24時間・365日、顧客対応できるようになる

電話受付の対応時間には制限があるため、自分がある商品・サービスの購入を検討しているとき、あるいはすでに購入して使用しているときのことを想像してみてください。
「商品・サービスについて知りたいことがあり、電話で問い合わせようとしたら、すでに受付時間が終了していた…」という経験はないでしょうか?
あるいは、「そもそも土日・祝日だったので、電話自体を受付けていなかった…」というケースも多いと思います。「働いている曜日や時間帯の都合上、受付の対応時間内にはとても電話できない…」という方もいるかもしれません。
せっかく興味を持った商品・サービスについての疑問がすぐに解決できないのは、非常にもどかしいものです。
企業ホームページに答えを掲載していても、なかなか顧客は求めている情報に到達できない。「それなら、企業ホームページに『よくある質問』や『FAQ』を掲載しておけば問題ないのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。確かにそれらのコンテンツを整備することで、ある程度のお問い合わせ省力化は期待できます。
しかし、たとえ企業ホームページ内に求めている答えが掲載されていても、そこに到達できない顧客も多数存在するのが現状です。みなさんにもホームページ内の各コンテンツを散々探し回ったあげく、求めている情報が見つからずに諦めてしまった経験があるのではないでしょうか?ホームページ内に単に情報を掲載するだけでは、それを求めている顧客はなかなか到達しづらいのです。
お問い合わせメールフォームでは、回答が届くまでに待ち時間が発生する。一応、企業ホームページにお問い合わせのメールフォームなどがあれば、質問・疑問をすぐに送信することはできるのですが、回答が返ってくるのは結局、問い合わせ先の企業の営業時間・営業日を迎えてからです。
つまり、メールフォームの場合でも疑問の解消まで、ある程度の待ち時間が発生する点では電話と変わりがありません。
商品・サービスについて知りたいことがすぐにわからないのは、顧客に大きなストレスを与え受注率や顧客満足度にも影響します。しかし、企業が電話受付の対応時間や日数を増やすのは難しい一方、次は企業側の立場で考えてみましょう。
24時間・365日対応できるように電話対応スタッフを常時配備させるのが理想論としては正しいのかもしれません。ですが、それには多大な業務負担が生じてしまいます。また、新たなスタッフの給料・残業代・時間外手当・休日手当が発生するので人件費が膨れ上がってしまい、現実的ではないでしょう。
そもそも、この人手不足の時代に対応スタッフを新規採用できるかの時点で疑問符がつきます。
チャットボット導入でコストを抑えて顧客満足度を向上!これまでは、顧客側・企業側ともに以上のような問題を抱えていましたが、チャットボットはその解決策になりえます。
企業ホームページにチャットボットを設置しておけば、深夜や早朝・休日であっても顧客は自分の好きなタイミングで商品・サービスについての疑問を解消できるようになります。電話とちがって受付時間を気にする必要はありませんし、メールのように返信が来るまで待つこともありません。
簡単な疑問であれば即時解決できますので、社員に負担をかけることなく顧客満足度が向上します。
「商品・サービスについて知りたいことがあり、電話で問い合わせようとしたら、すでに受付時間が終了していた…」という経験はないでしょうか?
あるいは、「そもそも土日・祝日だったので、電話自体を受付けていなかった…」というケースも多いと思います。「働いている曜日や時間帯の都合上、受付の対応時間内にはとても電話できない…」という方もいるかもしれません。
せっかく興味を持った商品・サービスについての疑問がすぐに解決できないのは、非常にもどかしいものです。
企業ホームページに答えを掲載していても、なかなか顧客は求めている情報に到達できない。「それなら、企業ホームページに『よくある質問』や『FAQ』を掲載しておけば問題ないのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。確かにそれらのコンテンツを整備することで、ある程度のお問い合わせ省力化は期待できます。
しかし、たとえ企業ホームページ内に求めている答えが掲載されていても、そこに到達できない顧客も多数存在するのが現状です。みなさんにもホームページ内の各コンテンツを散々探し回ったあげく、求めている情報が見つからずに諦めてしまった経験があるのではないでしょうか?ホームページ内に単に情報を掲載するだけでは、それを求めている顧客はなかなか到達しづらいのです。
お問い合わせメールフォームでは、回答が届くまでに待ち時間が発生する。一応、企業ホームページにお問い合わせのメールフォームなどがあれば、質問・疑問をすぐに送信することはできるのですが、回答が返ってくるのは結局、問い合わせ先の企業の営業時間・営業日を迎えてからです。
つまり、メールフォームの場合でも疑問の解消まで、ある程度の待ち時間が発生する点では電話と変わりがありません。
商品・サービスについて知りたいことがすぐにわからないのは、顧客に大きなストレスを与え受注率や顧客満足度にも影響します。しかし、企業が電話受付の対応時間や日数を増やすのは難しい一方、次は企業側の立場で考えてみましょう。
24時間・365日対応できるように電話対応スタッフを常時配備させるのが理想論としては正しいのかもしれません。ですが、それには多大な業務負担が生じてしまいます。また、新たなスタッフの給料・残業代・時間外手当・休日手当が発生するので人件費が膨れ上がってしまい、現実的ではないでしょう。
そもそも、この人手不足の時代に対応スタッフを新規採用できるかの時点で疑問符がつきます。
チャットボット導入でコストを抑えて顧客満足度を向上!これまでは、顧客側・企業側ともに以上のような問題を抱えていましたが、チャットボットはその解決策になりえます。
企業ホームページにチャットボットを設置しておけば、深夜や早朝・休日であっても顧客は自分の好きなタイミングで商品・サービスについての疑問を解消できるようになります。電話とちがって受付時間を気にする必要はありませんし、メールのように返信が来るまで待つこともありません。
簡単な疑問であれば即時解決できますので、社員に負担をかけることなく顧客満足度が向上します。
メリット3.同時に多数のお問い合わせに対応できる

お電話でのお問い合わせでは、1人の顧客が電話をかけた際にはかならず最低1人の社員が対応しなければいけません。
同時に複数の顧客が電話をかけてきた場合には、電話回線が混み合うケースも発生します。顧客側からすると、何度かけても電話中で全然つながらない状態には、非常にストレスを感じます。
それが原因で結局、商品・サービスの購入や来店を諦めた…というケースも起きるでしょう。電話は同時に多数のお問い合わせを受けるのには向いておらず、支障がでてしまうのです。その点、チャットボットは同時に何人の顧客から問い合わせが来ても、問題なくスムーズに回答できます。
会社側にとっては電話対応の労力を大きく削減し、顧客側にとっては電話の混雑による待ち時間が発生しません。すぐに疑問を解消できるので顧客もストレスを感じることなく、満足度が向上します。
同時に複数の顧客が電話をかけてきた場合には、電話回線が混み合うケースも発生します。顧客側からすると、何度かけても電話中で全然つながらない状態には、非常にストレスを感じます。
それが原因で結局、商品・サービスの購入や来店を諦めた…というケースも起きるでしょう。電話は同時に多数のお問い合わせを受けるのには向いておらず、支障がでてしまうのです。その点、チャットボットは同時に何人の顧客から問い合わせが来ても、問題なくスムーズに回答できます。
会社側にとっては電話対応の労力を大きく削減し、顧客側にとっては電話の混雑による待ち時間が発生しません。すぐに疑問を解消できるので顧客もストレスを感じることなく、満足度が向上します。
メリット4.社員ごとの顧客対応のクオリティのバラつきに悩まされない

一口に顧客対応といっても、その業務をスムーズかつ十分なクオリティでこなすのは決して簡単ではありません。
社会人としての最低限の受け答えのマナーや、声のトーンのコントロール、コミュニケーション能力、商品・サービスについての知識などが一定レベルないと、顧客に不信感やストレスを与えてしまい、場合によってはクレームにも発展してしまいます。
ですが、実際は社員によって電話対応の巧拙にはバラつきが出てしまうのが現実です。さらに新入社員やアルバイトに、最初からベテラン社員レベルの完璧な電話対応を求めるのも無理があるでしょう。
チャットボットならば、対応のクオリティに差が出ないので、常に安定した回答を顧客に提供できます。これにより人的原因による顧客への悪印象の発生や、クレームの発生を防止できます。
社会人としての最低限の受け答えのマナーや、声のトーンのコントロール、コミュニケーション能力、商品・サービスについての知識などが一定レベルないと、顧客に不信感やストレスを与えてしまい、場合によってはクレームにも発展してしまいます。
ですが、実際は社員によって電話対応の巧拙にはバラつきが出てしまうのが現実です。さらに新入社員やアルバイトに、最初からベテラン社員レベルの完璧な電話対応を求めるのも無理があるでしょう。
チャットボットならば、対応のクオリティに差が出ないので、常に安定した回答を顧客に提供できます。これにより人的原因による顧客への悪印象の発生や、クレームの発生を防止できます。
メリット5.新規お問い合わせやコンバージョンの獲得率向上

チャットボットをホームページに掲載すると、訪問者が自分の疑問を即座に解消できるため、顧客満足度が向上します。
「商品・サービスについて知りたいことがあるけど、わざわざ電話やメールで問い合わせするのは面倒だな…」という顧客も、チャットボットには気軽に質問して疑問を解消してくれます。
その結果、資料請求や無料相談などのコンバージョンを起こす確率が高まり、新規顧客を獲得しやすくなります。
また、弊社のDSチャットボットのようなツールを利用すれば、お客様の質問の内容に合致した資料をレコメンドすることも可能です。
さらにチャットボットに質問をまだされていない状態であっても、訪問者が閲覧しているページの内容に合わせたバナーを自動的に表示することできます。
たとえば、建築会社のホームページにおいて、訪問者が新築についてのページを見ているときには「はじめての家づくり」などのお役立ち資料のバナーを表示し、逆にリフォームのページを見ているときは「賢くお得にリフォームを実施するポイント」などの資料のバナーを表示する…といった、バナーの出し分けが可能です。
これによって、コンバージョンの獲得がより促進されます。
メリット6.顧客が質問するハードルが下がる

商品・サービスの購入を検討中の顧客のなかには、「商品・サービスについて知りたいことがあるけど、電話やメールで問い合わせするのは恥ずかしい…」「電話やメールでいちいち質問するのは面倒くさい」と考えている方もいます。
あるいは、企業ホームページ上のお問い合わせフォームからの質問では、名前やメールアドレス、電話番号などが必須項目になっていることが多いので、「個人情報や連絡先をこの段階では相手に渡したくない…」と考えて二の足を踏む顧客もいるでしょう。
チャットボットを導入すれば、機械が答えてくれるのでどんな質問でも気軽にできます。また、お問い合わせフォームのように個人情報・連絡先を打ち込む必要もないので、質問のハードルが格段に下がります。
チャットボット導入で顧客の疑問が解消される確率が上昇し、売上げアップにもつながりやすくなります。
あるいは、企業ホームページ上のお問い合わせフォームからの質問では、名前やメールアドレス、電話番号などが必須項目になっていることが多いので、「個人情報や連絡先をこの段階では相手に渡したくない…」と考えて二の足を踏む顧客もいるでしょう。
チャットボットを導入すれば、機械が答えてくれるのでどんな質問でも気軽にできます。また、お問い合わせフォームのように個人情報・連絡先を打ち込む必要もないので、質問のハードルが格段に下がります。
チャットボット導入で顧客の疑問が解消される確率が上昇し、売上げアップにもつながりやすくなります。
メリット7.会話データ蓄積による顧客理解度の明確化、マーケティング・経営への活用

チャットボットに顧客が打ち込んだ質問はすべてデータとして保存されます。これにより会社が今まで把握できていなかった隠れたニーズや、商品・サービス紹介のわかりづらいポイントなどを言語化された状態で理解でき、改善策を立案しやすくなります。
【チャットボット経由の改善策立案の例】
- 「この点に疑問を持っているお客様が多いので、チラシやホームページに説明を追加しよう」
- 「この商品・サービスは意外と女性からの質問も多くてニーズがあるようだから、そちらをターゲットにしたページを作ってみよう」
チャットボット導入で、企業ホームページの改善はもちろん、営業活動・販売活動全体のPDCAもより回しやすくなるのです。
また、チャットボットなら顧客の細かなニーズを漏らさず把握できるので、新商品・新サービスの開発やマーケティング全般、経営全般を進化させる一助にもなります。
メリット8.採用活動も効率化 求職者の隠れたニーズも引き出せる

企業のなかには採用サイトや採用ページにチャットボットを設置して、採用業務の効率化を実現している例もあります。
人事担当の社員は採用シーズンを迎えると急激に業務量が増大します。
人事担当の社員は採用シーズンを迎えると急激に業務量が増大します。
チャットボット導入で求職者からの単純なお問い合わせには自動的に回答してもらうことで、繁忙期の負担を軽減できます。
メリット9.業務の属人化の防止と、ナレッジの蓄積

さらにチャットボットには会社の業務の属人化を防ぐ機能もあります。
みなさんの職場を思い浮かべてみてください。商品・サービスについて詳しい社員に質問やお問い合わせが集中し、その人しか答えられないという事態はありませんか?
これが業務の属人化と呼ばれる現象です。
とくに中小企業にありがちなのが、「商品・サービスについて熟知している生き字引のような社員がいて、その人が通常どおり働いているときは問題なかったけれど、病気などで休んだら途端に仕事が回らなくなり、退職したら職場全体がパニック状態になってしまった…」というパターンです。
このように業務が属人化していると、お問い合わせのキーマンが退職した際に貴重なナレッジが喪失してしまい、その回復までに多大な時間を要することになります。
チャットボットを導入して社内のナレッジを蓄積・共有することで、業務の属人化を抑制し、お問い合わせのキーマンとなる社員の負担を大きく軽減できます。
「自分がいないと仕事が回らなくなるから…」と有給休暇を取るのを遠慮した社員も、旅行や子どもの行事などに参加しやすくなり、働き方改革が実現します。
みなさんの職場を思い浮かべてみてください。商品・サービスについて詳しい社員に質問やお問い合わせが集中し、その人しか答えられないという事態はありませんか?
これが業務の属人化と呼ばれる現象です。
とくに中小企業にありがちなのが、「商品・サービスについて熟知している生き字引のような社員がいて、その人が通常どおり働いているときは問題なかったけれど、病気などで休んだら途端に仕事が回らなくなり、退職したら職場全体がパニック状態になってしまった…」というパターンです。
このように業務が属人化していると、お問い合わせのキーマンが退職した際に貴重なナレッジが喪失してしまい、その回復までに多大な時間を要することになります。
チャットボットを導入して社内のナレッジを蓄積・共有することで、業務の属人化を抑制し、お問い合わせのキーマンとなる社員の負担を大きく軽減できます。
「自分がいないと仕事が回らなくなるから…」と有給休暇を取るのを遠慮した社員も、旅行や子どもの行事などに参加しやすくなり、働き方改革が実現します。
メリット10.外国語での対応を大幅に効率化し、販路拡大や人材獲得にもつながる

先述したように、AIチャットボットを活用すれば、外国語の問い合わせ対応を大幅に効率化できます。
外国語に堪能なスタッフが少ない会社では、海外からのお問い合わせ対応には、たとえ1件でも膨大な時間を割かれます。
また、「英語には何とか対応できても、中国語やベトナム語だとどうしようもない…」というケースも多いでしょう。
こういった言語のバリア(ランゲージバリア)は、各企業がビジネス目標を達成するうえでの障害になっています。
【言語バリアによるビジネスや業務の阻害例】
- 海外に向けて販路を拡大したい→しかし、外国語に堪能な従業員が少ないので、海外からの質問に対応しづらい…
- 外国人労働者を採用して人手不足を解消したい→外国人の求職者に自社の魅力や働き方を具体的に伝える手段がない…
- (学校・教育機関などの業種の場合)留学生を積極的に受け入れたい→自分たちの学校について外国語で伝えるのが難しく、質問を受けても対応しきれない
- (病院・介護などの業種の場合)在留外国人の患者さんも増えてきているので、きちんと対応したい→初診の流れや、対応できる症例などをうまく外国語で伝えられない…
AIチャットボットを活用すれば、自社のホームページやPDF書類を読み込ませるだけで、外国語の質問に対してチャットボットが自動で回答してくれます。
そのため各言語に精通したスタッフがいなくても簡単に対応できるので、大幅に業務を効率化できます。
また、海外の顧客や訪日外国人・在留外国人も、商品・サービスについて気になることがあれば、自分たちの言語で気兼ねなく質問できるようになります。
これにより、海外顧客の獲得や売上げアップを実現しやすくなるでしょう。
メリット11.昨今増加している電話が苦手な従業員・顧客の負担を減らせる
20代~30代のうち、50%以上が電話に苦手意識を持っている

昨今は若年層を中心に電話が苦手な人が増えている点も、チャットボットのメリットが大きくなっている理由のひとつです。
実際、アンケートのデータによれば20代~30代の半分近くが、電話でのコミュニケーションに苦手意識を持っていることがわかります。
出典:若者世代は電話が苦手ってホント? 電話よりもメッセージ派にその理由を聞いてみた(ソフトバンクニュース)
こちらのグラフによれば、20代のうち6割近くが電話に苦手意識を感じています。また、30代でも50%近くが苦手意識を感じているという結果になっています。
もちろんこれから年月が経っていけば、この20代は30代になりますし、30代は40代になりますので、いずれ電話に苦手意識を持つ人が多数派になっていくと予想できます。
以上の状況を踏まえると、電話対応を大きな負担に感じる従業員は今後確実に増えていくと思われます。
実際、アンケートのデータによれば20代~30代の半分近くが、電話でのコミュニケーションに苦手意識を持っていることがわかります。
出典:若者世代は電話が苦手ってホント? 電話よりもメッセージ派にその理由を聞いてみた(ソフトバンクニュース)
こちらのグラフによれば、20代のうち6割近くが電話に苦手意識を感じています。また、30代でも50%近くが苦手意識を感じているという結果になっています。
もちろんこれから年月が経っていけば、この20代は30代になりますし、30代は40代になりますので、いずれ電話に苦手意識を持つ人が多数派になっていくと予想できます。
以上の状況を踏まえると、電話対応を大きな負担に感じる従業員は今後確実に増えていくと思われます。
電話が苦手な見込み顧客や求職者を取り込み、従業員の負担や離職を減らすためにもチャットボットは有効

また、電話で問い合わせすることを敬遠する顧客や求職者も増えていくと予想されます。
実際に電話が苦手な方は、美容室や飲食店などではインターネット予約できる会社を探す傾向にあります。
参考ページ:「電話が怖い」取るのも掛けるのも苦手な若者増加中<U35スタイル>(北海道新聞)
そのため業務効率化だけでなく売上げの維持の側面でも、電話に頼ったコミュニケーションを見直していく必要があります。
チャットボットであれば、見込み顧客はチャットボットに質問して知りたい内容を自己解決してくれるため、電話対応の手間を大幅に削減できます。
そのため電話対応が苦手な従業員の負担を軽減して、働き方改革にもつながります。昨今は「電話対応が嫌なので会社を辞めたい」という従業員も年々増えているとのことなので、離職率の低下も実現できるでしょう。
参考ページ:「電話が嫌すぎる」退職も 電話を克服する方法は? メリットは?【就活イチ押しニュース】
また、電話が苦手な人々はテキストメッセージでのやり取りを好む傾向にあるので、チャットボットを設置することで、それらの層を顧客や求職者として取り込みやすくなります。
出典:若者世代は電話が苦手ってホント? 電話よりもメッセージ派にその理由を聞いてみた(ソフトバンクニュース)
実際に電話が苦手な方は、美容室や飲食店などではインターネット予約できる会社を探す傾向にあります。
参考ページ:「電話が怖い」取るのも掛けるのも苦手な若者増加中<U35スタイル>(北海道新聞)
そのため業務効率化だけでなく売上げの維持の側面でも、電話に頼ったコミュニケーションを見直していく必要があります。
チャットボットであれば、見込み顧客はチャットボットに質問して知りたい内容を自己解決してくれるため、電話対応の手間を大幅に削減できます。
そのため電話対応が苦手な従業員の負担を軽減して、働き方改革にもつながります。昨今は「電話対応が嫌なので会社を辞めたい」という従業員も年々増えているとのことなので、離職率の低下も実現できるでしょう。
参考ページ:「電話が嫌すぎる」退職も 電話を克服する方法は? メリットは?【就活イチ押しニュース】
また、電話が苦手な人々はテキストメッセージでのやり取りを好む傾向にあるので、チャットボットを設置することで、それらの層を顧客や求職者として取り込みやすくなります。
出典:若者世代は電話が苦手ってホント? 電話よりもメッセージ派にその理由を聞いてみた(ソフトバンクニュース)
チャットボットの用途・使い方
企業・団体でのチャットボットの用途・使い方は、主に社外向けと社内向けの2パターンに大別されます。
それぞれわかりやすく解説していきます。
【社外向けのチャットボットの使い方】
- 商品・サービスのFAQ(新規顧客向け)
- カスタマーサポート(既存顧客向け)
- 求職者への情報発信
- (学校・教育機関の場合)学生・受験生・留学生への対応・情報発信
【社内向けのチャットボットの使い方】
- 社内の問い合わせ対応
社外向けのチャットボットの使い方
商品・サービスのFAQ(新規顧客向け)

社外向けのチャットボット利用の代表例が、商品・サービスに関する顧客からの質問に自動回答させる使い方です。
とりわけ取り扱い商品・サービスの種類が多かったり、商品・サービスの内容が複雑だったりする場合に、効果を発揮します。
訪問者が疑問を自己解決してくれるため、「この会社なら自分の要望を実現してくれそうだ」と納得した訪問者だけが問い合わせをし、逆に「この会社の商品・サービスは自分の要望と合致しなさそうだ」と感じた訪問者は自然と離脱します。
そのため、受注に直結しやすい質の高い問い合わせのみを集められやすくなるでしょう。
カスタマーサポート(既存顧客向け)

既存顧客のカスタマーサポートにも、チャットボットの活用は有効です。
コールセンターの人材は慢性的に不足しているため、対応業務の効率化が急務になっています。
また、コールセンターやカスタマーセンターなどの専門部署を設けられない中小企業においては、在籍している従業員が兼務で顧客対応しないといけないため、労働生産性が悪化しやすいです。
簡単な質問はチャットボットで自己解決してもらい、複雑な問い合わせのみを人間が対応するようにすれば、大幅な業務削減を実現できます。
公共施設や観光施設、病院・介護施設の利用者への案内

県庁・市役所などの自治体、公民館などの公共施設など、不特定多数の方が利用する場所の案内にも、チャットボットは効果的です。
また観光施設のように初めて来訪する方が多数を占める場所でも、チャットボットをWebサイトに設置しておけば、事前に情報をチェックしてもらえるのでスムーズに観光してもらえるでしょう。
さらに、病院や介護施設などでも初診や入院・入所前に事前に準備しておくべきことなどを、チャットボットに質問してもらえれば、対応が簡便化します。
以上のような施設は、訪日外国人や在留外国人が利用することも多いため、多言語対応のチャットボットを活用するのがオススメです。
求職者への情報発信

顧客や利用者だけでなく、求職者への情報発信でもチャットボットは効果を発揮します。
まだエントリーや採用応募もしていない段階で、求職者側から質問を企業側に投げかけるのはハードルが高いです。
そのため「この会社は自分の希望と合致するか、よくわからないから応募をやめておこう」という意識が働きやすくなってしまいます。
しかし、チャットボットを導入すれば相手がAIやプログラムなので、求職者側は休暇・福利厚生などの直接は訊きづらい内容も気軽に質問しやすくなります。
また、求職者がチャットボットとの対応の過程で理解を深めて、「この会社の条件と自分の希望は合致しないな」と考えたとしても、ミスマッチを事前に減らせることになるので、選考の手間や早期離職のコスト・リスクを削減できるでしょう。
(学校・教育機関の場合)学生・受験生・留学生への対応・情報発信

受験生や在校生・留学生、保護者からの問い合わせは、入学案内・イベント情報・学費・履修・奨学金・留学制度など多岐にわたります。その多くはFAQ(よくある質問)で対応できる定型的な質問です。
チャットボットを導入すれば、これらの定型的な質問に自動で回答できるようになります。これにより、職員のみなさんが問い合わせ対応に費やす時間を大幅に削減でき、本来注力すべき業務に集中できるようになります。
また近年は海外からの留学生の受け入れも増えています。多言語対応が可能なチャットボットを導入すれば、日本語が堪能ではない留学生も安心して質問ができ、スムーズな情報収集が可能になります。これにより、留学生の不安を軽減し、より良い学生生活をサポートできます。
チャットボットを導入すれば、これらの定型的な質問に自動で回答できるようになります。これにより、職員のみなさんが問い合わせ対応に費やす時間を大幅に削減でき、本来注力すべき業務に集中できるようになります。
また近年は海外からの留学生の受け入れも増えています。多言語対応が可能なチャットボットを導入すれば、日本語が堪能ではない留学生も安心して質問ができ、スムーズな情報収集が可能になります。これにより、留学生の不安を軽減し、より良い学生生活をサポートできます。
社内向けのチャットボットの使い方
社内の問い合わせ対応

「あの書類はどこにあるんだろう?」「この手続きはどうやるんだっけ?」といった、業務や社内手続きに関する従業員の疑問は日常的に発生します。
これらの疑問に対して、チャットボットが24時間365日いつでも即座に回答することで、従業員は自分で情報を探し出す手間が省け、自己解決能力を高められます。
これにより、総務や人事、情報システム部といったバックオフィス部門が社内質問に対応する手間を大幅に削減できます。
【チャットボットが適している社内問い合わせの情報の例】
これらの疑問に対して、チャットボットが24時間365日いつでも即座に回答することで、従業員は自分で情報を探し出す手間が省け、自己解決能力を高められます。
これにより、総務や人事、情報システム部といったバックオフィス部門が社内質問に対応する手間を大幅に削減できます。
【チャットボットが適している社内問い合わせの情報の例】
- 交通費精算・有給休暇の申請・各種証明書の発行依頼などの方法
- 社内規定・福利厚生・ITツールの使い方・備品の発注方法
- 業務マニュアルや手順書
社内教育やオンボーディング

新入社員が会社に慣れるまでの期間をチャットボットがサポートします。
会社組織図、主要部署の役割、社内用語の解説、入社後の手続き案内など、新入社員が抱きやすい疑問にチャットボットが自動回答することで、スムーズな立ち上がりを支援します。
これにより先輩や教育係の社員の負担を大幅に削減できます。
会社組織図、主要部署の役割、社内用語の解説、入社後の手続き案内など、新入社員が抱きやすい疑問にチャットボットが自動回答することで、スムーズな立ち上がりを支援します。
これにより先輩や教育係の社員の負担を大幅に削減できます。
おすすめのチャットボット一覧
企業・団体の業務効率化に適した、おすすめのチャットボットサービスを紹介します。
【おすすめのチャットボットサービス】
【おすすめのチャットボットサービス】
- DSチャットボット
- AIチャットボットさくらさん
- ChatPlus
- sinclo
- KARAKURI chatbot
- HiTTO
DSチャットボット 初心者でも使いやすいAIチャットボット

弊社ディーエスブランドのAIチャットボット・DSチャットボットは、初心者でも簡単に運用できます。
ホームページ内の情報や、アップロードしたPDFの書類などのデータを読み取って自動で学習を進めるので、Q&Aシナリオ作成の手間がかかりません。
回答時には参考にしたページのURLなども付記されますので、サイト内の回遊率を高めることができ、資料請求やお問い合わせなどのコンバージョンの獲得にも貢献します。
また多言語対応のオプションもあり、英語・中国語・韓国語・ベトナム語など80以上の言語からの質問に対応できます。
シンプルでビジネスに使いやすいAIチャットボットをお求めなら、ぜひ以下からDSチャットボットの詳細をご覧ください。
AIチャットボットさくらさん 大企業や自治体に多数の導入実績

AIチャットボットさくらさんは、株式会社ティファナ・ドットコムが提供するAIチャットボットサービスです。
大企業向けのため非常に高機能で、専任のサポートチームが導入から運用まで一貫してサポートしてくれるので安心です。
最高裁判所や商船三井などの、自治体や大企業にも多数導入実績がある点も魅力のひとつです。
比較的に多額の予算を用意できて、多数のお問い合わせ業務が日々発生している企業にはおすすめのチャットボットです。
・AIチャットボットさくらさん公式サイト
大企業向けのため非常に高機能で、専任のサポートチームが導入から運用まで一貫してサポートしてくれるので安心です。
最高裁判所や商船三井などの、自治体や大企業にも多数導入実績がある点も魅力のひとつです。
比較的に多額の予算を用意できて、多数のお問い合わせ業務が日々発生している企業にはおすすめのチャットボットです。
・AIチャットボットさくらさん公式サイト
ChatPlus 導入数2万社以上の低価格で使えるチャットボット

ChatPlus(チャットプラス)は、チャットプラス株式会社が提供しているチャットボットサービスで、2万件以上の導入実績を誇ります。
低価格で利用できるのが最大の特長で、それでいて有人チャットやレポート機能など多彩な機能を備えているのが魅力です。
利用者が質問を入力している途中でサジェスト回答を表示する機能もあるので、利用者の疑問を短時間で解決できます。
低価格で利用できるのが最大の特長で、それでいて有人チャットやレポート機能など多彩な機能を備えているのが魅力です。
利用者が質問を入力している途中でサジェスト回答を表示する機能もあるので、利用者の疑問を短時間で解決できます。
sinclo 簡単で分かりやすいチャットボット型Web接客ツール

sinclo(シンクロ)は、株式会社エフ・コードが提供するシナリオ型チャットボットです。
訪問者の“今”に合わせたWeb接客で、コンバージョンの増加などサイトの成果を改善できます。
大きな特徴は、有人チャット機能も利用できるハイブリッド型のため、自動対応で解決できない問い合わせにも、その場で対応できる点です。また、管理画面はシンプルで分かりやすく、ノーコードで直感的に操作できるため、運用の手間もかかりません。
さらに、チャットログをAIが自動要約し、重要なやりとりを即座に把握できる「チャット履歴AI要約」機能も提供しています。
KARAKURI chatbot カスタマーサポートに特化したチャットボット

KARAKURI chatbotは、カラクリ株式会社が提供するAIチャットボットツールです。
最大の特長は、カスタマーサポートに特化したチャットボットであることです。
独自の大規模言語モデル(LLM)・「KARAKURI LM」を活用した自然な受け答えが可能なほか、複数テナントでの統合管理や、CRM(顧客関係システム)と連携させたパーソナライズ対応など、既存顧客向けの対応に役立つ機能が多数搭載されています。
会員情報の変更や返品の対応なども自動化できるので、カスタマーサポートへの負担を大幅に削減できます。
カスタマーサポート業務の効率化が主目的の方には、おすすめのチャットボットです。
・KARAKURI chatbot公式サイト
最大の特長は、カスタマーサポートに特化したチャットボットであることです。
独自の大規模言語モデル(LLM)・「KARAKURI LM」を活用した自然な受け答えが可能なほか、複数テナントでの統合管理や、CRM(顧客関係システム)と連携させたパーソナライズ対応など、既存顧客向けの対応に役立つ機能が多数搭載されています。
会員情報の変更や返品の対応なども自動化できるので、カスタマーサポートへの負担を大幅に削減できます。
カスタマーサポート業務の効率化が主目的の方には、おすすめのチャットボットです。
・KARAKURI chatbot公式サイト
HiTTO バックオフィス部門の業務効率化に特化したチャットボット

HiTTOは株式会社マネーフォワードが提供している、バックオフィス部門向けのチャットボットです。
以下のような会社・組織でよくある質問に自動回答することで、社内問い合わせ対応の手間を格段に効率化できます。
【チャットボットの活用で効率化できる社内問い合わせ対応業務の例】
- 「あのマニュアルはどこ?」などの社内規定や業務マニュアルに関する質問
- 「有給休暇の申請方法は?」などの人事・総務関連の質問
- 「このシステムの使い方教えて」などのIT関連の質問
日本中の企業のノウハウ、100万以上のデータを学習済みのため、最適な情報のカテゴリー分けが最初から完了しているため、あとはそこに自社の情報を追加していくだけで、簡単に運用をスタートできます。
日々、大量の社内問い合わせ対応が発生する大企業や大規模な組織には、オススメのチャットボットです。
なお、問い合わせ対応の効率化や顧客体験の向上を実現するAIチャットボット12選を以下の記事で紹介していますので、ご興味のある方はご覧ください。
チャットボットについてのよくある質問
Q1. チャットボットとは何ですか?
A1. チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ボット(ロボット)」を組み合わせた言葉で、人間に代わって自動で会話を行うコンピュータープログラムのことです。Webサイト上に設置されるか、LINEなどのメッセージアプリ上で運用されるケースが多いです。
お客様からのよくある質問に自動で回答することで、業務効率化や顧客体験の向上に役立ちます。
Q2. チャットボットの種類にはどのようなものがありますか?
A2. チャットボットは大きく分けて、以下の2種類があります。
【シナリオ型チャットボット】
あらかじめ設定された「Q&Aシナリオ」にもとづいて会話を進めるタイプのチャットボットです。「この質問が来たら、この回答を返す」というQ&Aシナリオを事前に登録しておくことで、求めている情報にお客様がたどりつきやすくなります。
【シナリオ型チャットボット】
あらかじめ設定された「Q&Aシナリオ」にもとづいて会話を進めるタイプのチャットボットです。「この質問が来たら、この回答を返す」というQ&Aシナリオを事前に登録しておくことで、求めている情報にお客様がたどりつきやすくなります。
欠点として、Q&Aシナリオの作成の難易度が高く、労力・負担も大きいことが挙げられます。
【AI型チャットボット(AIチャットボット)】
AI(人工知能)を搭載しており、お客様の質問の意図を理解して、自動的に適切な回答を生成するタイプのチャットボットです。過去の会話データや学習データにもとづいた、自然で柔軟な会話が可能です。
【AI型チャットボット(AIチャットボット)】
AI(人工知能)を搭載しており、お客様の質問の意図を理解して、自動的に適切な回答を生成するタイプのチャットボットです。過去の会話データや学習データにもとづいた、自然で柔軟な会話が可能です。
シナリオ型チャットボットとちがい、Q&Aシナリオの作成の手間がかからないのが最大のメリットです。また、外国語の質問への対応もしやすい点も優れています。
Q3. チャットボットを導入するメリットは何ですか?
A3. チャットボットを導入する主なメリットは以下の通りです。
顧客対応の効率化とコスト削減: お客様からのよくある質問に自動で回答できるため、電話やメールでの問い合わせ対応にかかる時間や人件費を削減できます。近年は電話対応を負担に感じている従業員が増えているため、ストレスの軽減や離職率の低下にも貢献します。
24時間365日対応: 営業時間外でもお客様の疑問に即座に回答できるため、顧客満足度の向上につながります。
顧客満足度の向上: 待ち時間なくスムーズに情報が得られることで、お客様のストレスを軽減し、利便性を高めます。
コンバージョン率の改善:お客様の顧客体験が向上するため、資料ダウンロードやお問い合わせ・無料相談などのコンバージョン数を増加しやすくなります。
問い合わせ内容のデータ蓄積: どのような質問が多いのか、どのような情報が求められているのかといったデータを収集・分析することで、Webサイトの改善や商品・サービスの改善に役立ちます。
Q4. 中小企業でもチャットボットは導入できますか?
A4. はい、中小企業でもチャットボットの導入は十分可能です。
最近では、プログラミングの知識がなくても簡単にチャットボットを作成・導入できるサービスが増えています。まずは、「よくある質問」などのコンテンツを自動化するところから始めるなどスモールスタートで導入するのがよいでしょう。
最近では、プログラミングの知識がなくても簡単にチャットボットを作成・導入できるサービスが増えています。まずは、「よくある質問」などのコンテンツを自動化するところから始めるなどスモールスタートで導入するのがよいでしょう。
また、Q&Aシナリオの作成にはかなりの時間と労力がかかりますので、AIチャットボットの導入もおすすめです。
Q5.おすすめのチャットボットサービスは何ですか?
使い方・用途によって最適なチャットボットサービスは変わりますが、以下が使いやすくておすすめです。
- DSチャットボット:初心者でも使いやすいAIチャットボット
- AIチャットボットさくらさん:大企業や自治体に多数の導入実績
- ChatPlus:導入数2万社以上の低価格で使えるチャットボット
- KARAKURI chatbot:カスタマーサポートに特化したチャットボット
- HiTTO:バックオフィス部門の業務効率化に特化したチャットボット
Q6. チャットボットを導入する際の注意点はありますか?
A6. チャットボット導入を検討する際に注意すべきなのは主に以下の2点です。
【チャットボットの用途と最適なツールの選定】
「チャットボットを社外向け・社内向けのどちらで中心に使うのか」・「社外向けに利用する場合は新規顧客向けか、既存顧客向けか」など、利用シーンを明確にしてから導入を検討しましょう。
【チャットボットの用途と最適なツールの選定】
「チャットボットを社外向け・社内向けのどちらで中心に使うのか」・「社外向けに利用する場合は新規顧客向けか、既存顧客向けか」など、利用シーンを明確にしてから導入を検討しましょう。
「このチャットボットツールは社外向けの対応が得意」などの特性がありますので、自社の目的とマッチするチャットボットツールを選んでください。
【Q&Aシナリオ作成をどのように実現するか】
Q&Aシナリオの作成には、商品・サービスに関する深い知識と高い顧客理解度が必須です。そのため作成の難易度が意外に高く、時間・労力の負担も大きいものになります。
【Q&Aシナリオ作成をどのように実現するか】
Q&Aシナリオの作成には、商品・サービスに関する深い知識と高い顧客理解度が必須です。そのため作成の難易度が意外に高く、時間・労力の負担も大きいものになります。
チャットボットを運用するには、Q&Aシナリオ作成を誰が担当するのか、必要な時間をどのように確保するのかも綿密に決めておきましょう。
Q&Aシナリオ作成に人材・時間などのリソースを割けない場合は、AIチャットボットの利用がおすすめです。WebページやPDFの書類などを読み込ませるだけで、生成AIが自動回答してくれるためQ&Aシナリオ作成の手間が不要になります。
今後の人手不足・グローバル化に対応するには、チャットボットの活用が効果的!

ここまでチャットボットの意味や仕組み、メリット・使い方について詳しく解説してきました。
日本は少子化による人手不足が進行しているため、業務の効率化が不可欠です。また、国内市場の縮小が予想されるため、海外需要の掘り起こしも売上げを維持していくには必須になっていきます。
外国人労働者の活用を検討している企業・組織も多いでしょう。
そんな状況で、対応を自動化できるチャットボットは大きな効果を発揮します。
AIチャットボットであれば、煩雑なQ&Aシナリオ作成の手間は不要で手軽に導入できます。また、多言語対応も簡単なのでぜひ導入を検討してみてください。
日本は少子化による人手不足が進行しているため、業務の効率化が不可欠です。また、国内市場の縮小が予想されるため、海外需要の掘り起こしも売上げを維持していくには必須になっていきます。
外国人労働者の活用を検討している企業・組織も多いでしょう。
そんな状況で、対応を自動化できるチャットボットは大きな効果を発揮します。
AIチャットボットであれば、煩雑なQ&Aシナリオ作成の手間は不要で手軽に導入できます。また、多言語対応も簡単なのでぜひ導入を検討してみてください。
なお、弊社でもAIチャットボット・DSチャットボットを提供しております。
興味のある方はぜひ以下から詳細をご覧ください。
興味のある方はぜひ以下から詳細をご覧ください。