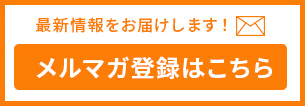OODAループとは? PDCAとのちがいと中小企業のWebマーケティングでの活用法
更新日:2025.03.07

昨今、変化が激しいビジネスシーンに対応するためのフレームワークとして、OODAループ(ウーダループ)が注目されています。
OODAループの意味やメリット、よく比較されるPDCAとのちがいについて初心者向けに紹介します。
また、OODAループは中小企業のWebマーケティングにおいて最適なフレームワークです。
OODAループを活用してホームページ経由での売上げを最大化する方法についても紹介しますので、成果を効率的に獲得したい方はぜひご覧ください。
目次
[非表示]
- OODAループとは?
- OODAループの4つのプロセス
- OODAループのビジネスでの活かし方
- OODAループのメリット
- OODAループとPDCAのちがい
- PDCAが中小企業のWebマーケティングで使いづらい理由
- 1.中小企業にはマーケティングやIT専門の部署がない
- 2.中小企業のホームページではチェックに必要なデータが集まらない
- 中小企業のホームページ担当者はほかの業務も兼任しているので、計画どおりに作業が進むことは少ない
- 中小企業のWebマーケティングでは綿密な計画どおりに行動するよりも、荒削りでも活動量・発信量を上げることのほうが重要
- 中小企業のホームページ担当者は大抵1人なので、自発的に動けるOODAループがオススメ
- 1.中小企業ではPDCAよりも、観察から始まるOODAループのほうがより効率的な施策を実行できる
- 2.頻繁なチェックの作業は、中小企業のWebマーケティングでは不要
- 中小企業のWebマーケティングでのOODAループ
- 1.観察(Observe)…競合他社・同業他社のホームページの分析
- 2.状況判断(Orient)…他社のサイトから共通点を見いだして抽象化
- 3.意思決定(Decide)…どの施策から優先的に実施すべきかの順位付け
- 4.行動(Act)…ホームページを実際に編集
- OODAループを活用して、Webマーケティングの成果を最大化しよう!
- あわせて読みたい記事
- 国産ホームページサービス満足度No.1のおりこうブログで、自社サイトを開設・リニューアル!
OODAループとは?

OODAループ(ウーダループ)とは「観察(Observe)→状況判断(Orient)→意思決定(Decide)→行動(Act)」という4つのステップを繰り返すことで、素早く適切な判断を下すための考え方です。変化が激しい状況にも対応しやすいため、ビジネスシーンで注目されているフレームワークです。OODAサイクルとも呼ばれます。
OODAループは、もともとは空軍のパイロットが戦闘中の判断を速くするために考え出されたものですが、今では販売戦略の立案や新商品の企画など、様々な場面で活用できます。
大切なのは、この4つのステップを意識しながら、素早く回すことです。状況が変化したら、また新しい観察から始めるという具合に、ループとして回し続けることで、より良い判断ができるようになります。
OODAループは、もともとは空軍のパイロットが戦闘中の判断を速くするために考え出されたものですが、今では販売戦略の立案や新商品の企画など、様々な場面で活用できます。
大切なのは、この4つのステップを意識しながら、素早く回すことです。状況が変化したら、また新しい観察から始めるという具合に、ループとして回し続けることで、より良い判断ができるようになります。
OODAループの4つのプロセス
OODAループの4つのプロセスを、身近な例を交えながら分かりやすく説明します。
1.観察(Observe) まわりの状況を見る
これは「何が起きているのか」を見る段階です。まわりを観察したり、リサーチしたりして情報を集めます。
【身近な具体例】
- カフェでお茶を飲むとき、メニュー表の内容や店内の混み具合を見る
- 道を歩いているとき、信号や他の歩行者の動きを見る
- スマホを買うとき、色々な機種の性能やデザインを調べる
2.状況判断(Orient) 状況を理解する
見た情報をもとに「今どういう状況なのか」を考える段階です。情報に合致する仮説を立案します。
【身近な具体例】
- カフェが混んでいるのは、ランチタイムだからかな
- 向こうから自転車が来ているから、このまま歩くと危ないな
- この機種は高いけど、カメラ性能が良くて写真をよく撮る自分には合っているかも
3.意思決定(Decide) どうするか決める
理解した状況をもとに「これからどうするか」を決める段階です。仮説にフィットする最適な選択を採ります。
【身近な具体例】
- 混んでいるから、テイクアウトにしよう
- 自転車が通り過ぎるまで、少し待とう
- カメラ性能重視で、この機種にしよう
4.行動(Act) 実際に動く
決めたことを実際に行動に移す段階です。
【身近な具体例】
- テイクアウトの列に並ぶ
- その場で立ち止まる
- お店で商品を購入する
OODAループを状況に対応しながら何度も回すのが重要
この4つのステップは、1回で終わりではありません
たとえば、先程のカフェでコーヒーをテイクアウトするときの例で考えてみましょう。
【カフェに並んだあとでOODAを再ループさせるときの例】
- テイクアウトの列に並んでみたら(Act)、
- 思ったより列が長かったことに気づいて(Observe)、
- 「このまま待つと予定に遅れそうだ」と判断し(Orient)、
- 「やっぱり別のお店にしよう」と決めて(Decide)、
- 別のお店に向かう(Act)
以上のように状況に応じてすばやく判断し、OODAループを繰り返していきます。
完璧な判断を目指すあまり、考えすぎて行動が遅くなってしまうのは良くありません。
状況は常に変化しているのでスピード感を持って判断し、行動することが大切です。また、同じような状況を何度も経験することで、よりすばやく適切な判断ができるようになっていきます。
このように、OODAループは普段の生活でも無意識のうちにおこなっていますが、これをビジネスの現場で意識的に実施することで、より効果的な経営計画や販売戦略を立案できます。
OODAループのビジネスでの活かし方
OODAループをビジネスの現場で活かすにはどうすればよいのでしょうか?
新商品の企画・リリースを例に、OODAループの4つのプロセスを具体的に説明していきます。
1.観察(Observe) 情報を集める
まずは競合調査や、実際に顧客と接している営業担当者などから情報を収集していきます。
【観察(Observe)の手法】
- 競合調査:競合製品の特徴や価格帯を調べる
- 顧客の声:営業社員・サポートセンターの従業員へのヒアリング、SNSでの情報収集
- トレンド分析:業界の最新動向、流行している機能やデザイン
- 自社の状況:技術力、生産技術(サービスの提供能力)、販売チャネル(商流)の確認
2.状況判断(Orient) 集めた情報を分析・理解する
次に得られた情報をもとに仮説を立てていきます。自社の商品・サービスが優位性を発揮できる仮説を立案しましょう。
【状況判断(Orient)で立案する仮説の例】
- 「この価格帯の商品が売れている」
- 「顧客は○○という機能を求めている」
- 「競合他社にない △△ という特徴を出せそう」
- 「自社の強みを活かせる市場がある」
3.意思決定(Decide) 方針を決める
状況判断のプロセスで立てた仮説をもとに、最適な打ち手を策定します。
【意思決定(Decide)の方針例】
- ターゲット層の決定:「20-30代の女性をメインターゲットにしよう」
- 商品コンセプト:「手軽に使える高機能モデル」
- 価格設定:「競合より高付加価値・高価格帯で差別化」
- 販売戦略:「WebサイトやSNSを活用したプロモーション展開」
4.行動(Act) 実際に進める
施策を実行するプロセスです。実際の開発~プロモーションを方針に従って推進します。
【行動(Act)の施策例】
- 商品開発:設計、試作品の製作
- テスト:品質検査、ユーザーテスト実施
- 製造:量産体制の確立
- プロモーション:広告クリエイティブの作成、WebサイトやSNSを駆使した情報発信
ビジネスシーンに当てはめた場合の具体例
業務のDX化に役立つツールを販売している会社の場合を想定して、具体例を以下に紹介します。
【業務のDX化ツールのマーケティングを実施する場合のOODAループの例】
- 観察(Observe):アンケートや営業担当者へのヒアリングで、顧客が紙・FAX中心の作業を課題に感じていることが発覚
- 状況判断(Orient):「自社のDX化ツールのこの機能を少し改良すれば、ペーパーレス化が実現できそうだ!」と判断
- 意思決定(Decide):「ペーパーレス化を前面に打ち出した、バージョンアップ版の製品をリリースしよう」と決定
- 行動(Act):実際にDX化ツールを開発してリリース
その後は新たなループへと移行していきます。
【業務のDX化ツールのマーケティングを実施する場合に、OODAループを繰り返す場合の例】
- 観察(Observe):顧客アンケートや営業社員へのヒアリングで「操作方法がわかりづらいので、UI(ユーザーインターフェイス)の改善が必要」とわかる
- 状況判断(Orient):操作面でわかりづらさや誤解を生んでいる箇所がどこなのかを特定する
- 意思決定(Decide):UIの修正を決定
- 行動(Act):修正版をリリース
以上のようにOODAループを繰り返してビジネスを推進させることで、スピード感のある販売活動が可能になります。
※なお、弊社ではホームページ運営やWebマーケティングに必要な用語を、初心者向けに解説した資料を用意しております。以下から無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
OODAループのメリット
迅速な意思決定とアクションができる
OODAループの最大のメリットが、迅速に意思決定できることです。
綿密な計画を練ってから動き出すのとちがい、観察ベースで仮説を立ててスピーディーに実行できるので、アクションまでのスパンが短くなります。
社内に知見が蓄積されていない状態でも行動しやすい
また、綿密な計画を立案するには、社内に必要な情報・データ・知見が利用しやすい状態で蓄積されていることが前提になります。
しかし多くの中小企業においては、情報が言語化・データ化されていないことも多いため、適切な計画の立案自体がそもそも困難です。
しかしOODAループであれば、リサーチからステップを進められるので、最初の計画立案の時点でつまずいて何も進まなくなるリスクが少なくなります。
しかしOODAループであれば、リサーチからステップを進められるので、最初の計画立案の時点でつまずいて何も進まなくなるリスクが少なくなります。
変化が激しい状況でも、柔軟かつ臨機応変に対応できる
現代のビジネスの現場では、新しい競合他社の登場やグローバル化、新技術の開発、新SNSの台頭による広告手段の変容など、さまざまな変化が立て続けに起こります。
OODAループは観察ベースで動き出しが決まるので、変化が激しい状況でも的確な施策を立案できます。
OODAループは観察ベースで動き出しが決まるので、変化が激しい状況でも的確な施策を立案できます。
現場の担当者が自発的に動きやすく、経験とともに判断力が向上する
OODAループは綿密な計画に沿って動くのではなく、現場の状況を観察したのちにアクションの方向性を決定するので、現場主導の意思決定が可能になります。
リアルタイムで自発的な行動が可能になるので、とりわけ少人数、あるいは担当者が1人だけの現場には、とても適しています。
また上層部や上長からの指示を待ってから行動するのではなく、自発的にアイディアを出して実行するので、経験を積めば積むほど従業員の判断力が向上していくのも大きなメリットです。
リアルタイムで自発的な行動が可能になるので、とりわけ少人数、あるいは担当者が1人だけの現場には、とても適しています。
また上層部や上長からの指示を待ってから行動するのではなく、自発的にアイディアを出して実行するので、経験を積めば積むほど従業員の判断力が向上していくのも大きなメリットです。
※なお、OODAループと同じく、中小企業のマーケティングに適しているフレームワークとしてランチェスター戦略が挙げられます。興味のある方は以下をご覧ください。
OODAループとPDCAのちがい
OODAループと比較されることの多いフレームワーク、PDCAとは?

OODAループとよく比較されるフレームワークにPDCAがあります。
PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つの段階を繰り返すことによって、業務やプロジェクトを継続的に改善していくためのフレームワークです。
- Plan(計画):目標を設定し、それを達成するための具体的な計画を立てます
- Do(実行):計画に基づいて実際に行動します
- Check(評価):実行した結果を評価し、目標達成度や改善点を確認します
- Action(改善):評価結果に基づいて改善策を検討し、次のPlanに反映させます
PDCAサイクルを回すことで、業務やプロジェクトの効率化、品質向上、コスト削減などを実現することができます。
PDCAは工場での生産のように状況が変わらない環境では有効だが、変化が激しい環境では真価を活かせない
ただしPDCAは、工場での製品の生産のように、状況が変わらないことを前提とした領域では効果を発揮するのですが、変化が激しい環境ではうまく機能しないことが多いです。
次々に予測不能な事態が起こり、外部との相互作用が働く環境下では、最初のPである計画自体が途中で陳腐化するリスクが著しく高まります。
また、先述したように情報・データ・知見を適切に蓄積している会社でないと、有効な計画をそもそも立てられないというデメリットも存在します。
計画立案はPDCAの最初のステップなので、そこでつまずいてしまうと活動全体が停滞してしまうでしょう。
次々に予測不能な事態が起こり、外部との相互作用が働く環境下では、最初のPである計画自体が途中で陳腐化するリスクが著しく高まります。
また、先述したように情報・データ・知見を適切に蓄積している会社でないと、有効な計画をそもそも立てられないというデメリットも存在します。
計画立案はPDCAの最初のステップなので、そこでつまずいてしまうと活動全体が停滞してしまうでしょう。
OODAループは状況が移り変わり、外部からの影響を強く受ける環境下に適したフレームワーク
それに対して、OODAループは刻々と状況が移り変わり、外部要因が大きい環境下で力を発揮します。
さらに最初は観察から始まりますので、情報が蓄積されていない中小企業などでもとっつきやすいフレームワークだといえるでしょう。
とりわけ中小企業のWebマーケティングの現場においては、PDCAよりもOODAループのほうが明らかに適しています。その理由をこれからわかりやすく解説していきます。
さらに最初は観察から始まりますので、情報が蓄積されていない中小企業などでもとっつきやすいフレームワークだといえるでしょう。
とりわけ中小企業のWebマーケティングの現場においては、PDCAよりもOODAループのほうが明らかに適しています。その理由をこれからわかりやすく解説していきます。
※なお、マーケティングを基礎から勉強したい方は以下のページをご覧ください。
PDCAが中小企業のWebマーケティングで使いづらい理由
それではPDCAがなぜ中小企業のWebマーケティングにおいて使いづらいのか、その理由をわかりやすく説明します。
【PDCAが中小企業のWebマーケティングに適さない理由】
- 中小企業にはマーケティングやIT専門の部署がない
- 中小企業のホームページではチェックに必要なデータが集まらない
- 中小企業のホームページ担当者はほかの業務も兼任しているので、計画どおりに作業が進むことは少ない
それぞれ具体的に見ていきましょう。
1.中小企業にはマーケティングやIT専門の部署がない
マーケティングの知識がある人材が少ないので、最初から適切な計画を立てられる確率が低い

PDCAが中小企業のWebマーケティング(特に開設・改善のスタート段階)で使いづらい最大の理由が、中小企業にはマーケティング専門の部署やWebに詳しい人材が少ないため有効なプラン(計画)を立案するのが困難だからです。
つまりPDCAの最初のPの段階で、高確率でつまずいてしまいます。
先述したように商品の生産工程などでは実施すべき業務が明確なので、改善計画は比較的立案しやすくPDCAが適しています。
しかしWebマーケティングにおいては、施策の自由度や幅が格段に広いため、計画立案は難しいのです。
中小企業のWebマーケティングでは計画通りに進まなかった箇所の分析・改善がそもそも困難
工場の生産現場などでは、以下のように改善ポイントを明瞭に発見できます。
【生産現場の改善ポイント】
- ○○の工程にかかる作業時間がほかと比べて、○○分長い
- 不良品率が通常よりも○%高く、歩留まりが悪い
以上のように生産工程などでは課題や改善ポイントを明らかにしやすく、数値化も容易です。
ですが、Webマーケティングの分野においては「売り上げが低い」「新規顧客の獲得数が少ない」「ホームページのアクセス数が少ない」などの大雑把な課題・あるいは結果はわかるのですが、「なぜ、どのようなプロセスを経てこのような状態に陥っているのか?」をWebマーケティングの初心者が分析・言語化するのは至難の業といってよいでしょう。
そのため事前に社内で明確なプランを組み立てる有効性が、中小企業においては低いのが現状です。
2.中小企業のホームページではチェックに必要なデータが集まらない
中小企業のホームページの改善点は、分析以前に明確になっていることがほとんど

また、PDCAのキモは3番目のC、チェックにあります。
常に施策の成果を客観的に把握し、改善を重ねていくプロセスこそがPDCAの最大のメリットであり真骨頂です。
しかし中小企業のWebマーケティングにおいては、問題点はわざわざチェックしなくてもいいほど明確であることがほとんどです。
具体的にいえば、ほとんどの中小企業のホームページでは集客・アクセス数の不足が最大のボトルネックになっています。
これはテレビCMや新聞広告などの豊富なPR手段を利用できる大企業と比較して、中小企業は知名度・ブランド力で大きく劣るからです。
そのためWeb広告を使わない場合は、まずはSEO(検索エンジン最適化)やSNS経由で集客数を増加させないと中小企業のWebマーケティングでは何も始まりません。
参考ページ:SEOとは? 企業ホームページのSEO対策で集客する基本をわかりやすく解説
常に施策の成果を客観的に把握し、改善を重ねていくプロセスこそがPDCAの最大のメリットであり真骨頂です。
しかし中小企業のWebマーケティングにおいては、問題点はわざわざチェックしなくてもいいほど明確であることがほとんどです。
具体的にいえば、ほとんどの中小企業のホームページでは集客・アクセス数の不足が最大のボトルネックになっています。
これはテレビCMや新聞広告などの豊富なPR手段を利用できる大企業と比較して、中小企業は知名度・ブランド力で大きく劣るからです。
そのためWeb広告を使わない場合は、まずはSEO(検索エンジン最適化)やSNS経由で集客数を増加させないと中小企業のWebマーケティングでは何も始まりません。
参考ページ:SEOとは? 企業ホームページのSEO対策で集客する基本をわかりやすく解説
中小企業のWebマーケティングでは綿密な計画を立てるより、シンプルに即行動したほうがよい
そして、これはわざわざGoogleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを見なくても、最初からわかることです。
中小企業のホームページ経由で売り上げをアップさせるには、Web広告を使わない場合、文章を書いてページを増やしコンテンツSEOを狙う施策が最適解になります。
参考ページ:コンテンツSEOとは? メリットとデメリット、実施する際の具体的な手順をWebマーケティング初心者へ解説!
あるいはお問い合わせのメールフォームの項目が長すぎたり、わかりづらかったりといったコンバージョン周りの欠陥があることも多いですが、こちらもわざわざ計画を立てるまでもなくすぐに改善できる要素です。
※コンバージョンの意味や、獲得率を上げる方法については以下のページをご覧ください。
参考ページ:コンバージョン(CV)とは? Webマーケティングでの意味をわかりやすく解説
参考ページ:企業ホームページのお問い合わせ数・新規商談獲得数を増やす基本
参考ページ:コンバージョン率(CVR)とは? 意味と重要性、計算方法を解説
つまり中小企業のWebマーケティングでは精密な計画を立てるよりも、シンプルに即行動したほうがよいのです。
中小企業のホームページ経由で売り上げをアップさせるには、Web広告を使わない場合、文章を書いてページを増やしコンテンツSEOを狙う施策が最適解になります。
参考ページ:コンテンツSEOとは? メリットとデメリット、実施する際の具体的な手順をWebマーケティング初心者へ解説!
あるいはお問い合わせのメールフォームの項目が長すぎたり、わかりづらかったりといったコンバージョン周りの欠陥があることも多いですが、こちらもわざわざ計画を立てるまでもなくすぐに改善できる要素です。
※コンバージョンの意味や、獲得率を上げる方法については以下のページをご覧ください。
参考ページ:コンバージョン(CV)とは? Webマーケティングでの意味をわかりやすく解説
参考ページ:企業ホームページのお問い合わせ数・新規商談獲得数を増やす基本
参考ページ:コンバージョン率(CVR)とは? 意味と重要性、計算方法を解説
つまり中小企業のWebマーケティングでは精密な計画を立てるよりも、シンプルに即行動したほうがよいのです。
中小企業のホームページ担当者はほかの業務も兼任しているので、計画どおりに作業が進むことは少ない

また、中小企業のホームページ担当者では専任が設置されていることはほとんどなく、大抵の場合はほかの業務も兼任しています。
基本的にほかの業務を優先してこなし、時間が余ったら企業ホームページの更新作業などに着手するというスタイルが多数派ではないでしょうか。
そのため急ぎの業務が入ればそちらの対応を優先せざるをえないホームページ担当者が大半ですので、緻密なホームページ運用計画を立てたとしてもうまくいかなかったり、途中で破綻したりする可能性が高いのです。
中小企業のホームページ運営ではマストで実施しないといけないガチガチの計画を立てるのは危険であり、業務の合間に更新作業やコンテンツの追加作業を進めることを前提とした、シンプルで柔軟性が高い計画のほうが適しています。
基本的にほかの業務を優先してこなし、時間が余ったら企業ホームページの更新作業などに着手するというスタイルが多数派ではないでしょうか。
そのため急ぎの業務が入ればそちらの対応を優先せざるをえないホームページ担当者が大半ですので、緻密なホームページ運用計画を立てたとしてもうまくいかなかったり、途中で破綻したりする可能性が高いのです。
中小企業のホームページ運営ではマストで実施しないといけないガチガチの計画を立てるのは危険であり、業務の合間に更新作業やコンテンツの追加作業を進めることを前提とした、シンプルで柔軟性が高い計画のほうが適しています。
中小企業のWebマーケティングでは綿密な計画どおりに行動するよりも、荒削りでも活動量・発信量を上げることのほうが重要

以上のように中小企業のホームページ運営では計画を立てるよりも、実際に手を動かして文章を書き、コンテンツを増やしたほうが集客数やアクセス数、売り上げに直結します。
PDCAサイクルを精密に回すことにばかり気を取られてしまうと、肝心の活動量が少なくなり結果を出せなくなってしまうでしょう。
まずは荒削りでもいいので、活動量・発信量を増やすことに注力してください。
中小企業のホームページ担当者は大抵1人なので、自発的に動けるOODAループがオススメ
先述したとおり、中小企業のホームページ担当者は1人であることがほとんどです。
そのため複数人で固定的な計画に取り組むのに適したPDCAよりも、担当者が自発的に行動できるOODAループのほうが効果的なのです。
これからOODAループが中小企業のWebマーケティングに適している理由をよりわかりやすく解説します。
【OODAループが中小企業のWebマーケティングに適している理由】
- 中小企業ではPDCAよりも、観察から始まるOODAループのほうがより効率的な施策を実行できる
- 頻繁なチェックの作業は中小企業のWebマーケティングでは不要
1.中小企業ではPDCAよりも、観察から始まるOODAループのほうがより効率的な施策を実行できる
マーケティング専門部署がない中小企業では、競合他社のホームページの分析から計画立案を進めたほうが効率的

OODAループとPDCAの一番のちがいが、OODAループでは最初のO(観察)のパートを重視していることです。
マーケティング専門の部署がない中小企業においては、この点が非常にマッチします。
マーケティングの基礎知識がない状態でゼロからプランを立案するよりも、競合他社のホームページを読みこんで他社の戦略を学んだほうがはるかに実践的で実行しやすいからです。
競合他社のホームページではどのようなコンテンツ・セールスコピーを掲載しているかを参考にしたほうが、社内で慣れないWebマーケティングプラン立案に四苦八苦するよりもはるかに簡単かつ効果的に集客や売り上げをアップできるでしょう。
検索上位の競合他社のホームページは、それらの社内ですでにPDCAを何周も回した結果に研ぎ澄まされていったもの
現在、GoogleやYahoo!の検索上位を獲得しておりWebマーケティングに成功している競合他社のホームページに掲載されている内容は、その会社がすでに内部で試行錯誤しPDCAを回したうえで研ぎ澄まされていったものです。
本気で集客数・売り上げアップを実現したいのであれば、これを参考にしない手はないでしょう。
単に社内のみで考えてPDCAを回すだけでは、すでに何周もPDCAを回して先行している競合他社には永遠に追いつけません。差はどんどん広がるばかりです。
つまり中小企業のWebマーケティングではPDCAを超えたスピードで、先行している競合他社にキャッチアップする必要があります。
本気で集客数・売り上げアップを実現したいのであれば、これを参考にしない手はないでしょう。
単に社内のみで考えてPDCAを回すだけでは、すでに何周もPDCAを回して先行している競合他社には永遠に追いつけません。差はどんどん広がるばかりです。
つまり中小企業のWebマーケティングではPDCAを超えたスピードで、先行している競合他社にキャッチアップする必要があります。
それを可能にするのがOODAループです。
2.頻繁なチェックの作業は、中小企業のWebマーケティングでは不要
OODAループはPDCAと比較して、チェックの機能が弱いと指摘されることもあるが、中小企業のホームページ運営ではあまり問題にならない
なお、OODAループとPDCAの大きなちがいとして、PDCAのC、つまりチェックの作業を独立して実施するかしないかがあります。
OODAループでは施策のチェック専用のステップがなく、2週目のO(観察)のステップに内包されています。
この点を指摘して、OODAループはPDCAと比較して改善のプロセスが弱いと言われることも多いです。
ですが、中小企業のWebマーケティングにおいては、そこはあまり大きなデメリットにはなりません。
なぜなら広告を使わないかぎり、中小企業のホームページではアクセス数などのデータの絶対量が少ないうえにそこまで急激に変化することはないため、頻繁にチェックの作業を入れてもあまり効果が得られないからです。
OODAループでは施策のチェック専用のステップがなく、2週目のO(観察)のステップに内包されています。
この点を指摘して、OODAループはPDCAと比較して改善のプロセスが弱いと言われることも多いです。
ですが、中小企業のWebマーケティングにおいては、そこはあまり大きなデメリットにはなりません。
なぜなら広告を使わないかぎり、中小企業のホームページではアクセス数などのデータの絶対量が少ないうえにそこまで急激に変化することはないため、頻繁にチェックの作業を入れてもあまり効果が得られないからです。
PR手段が多い大企業や、広告を利用している中小企業ならPDCAのチェック作業も有効だが、メインの集客手段がSEOである中小企業の場合にはアクセス数の増減の波がかなり小さい
知名度が高くテレビCMや新聞広告などの豊富なPR手段を持つ大企業であれば、データの絶対量が莫大ですので、WebマーケティングにおいてもPDCAのチェック作業は有効に機能します。
あるいは中小企業やスタートアップであっても、リスティング広告やSNS広告などのWeb広告や、新聞の折り込みチラシ・ダイレクトメール(DM)、ポスティングなどのリアルの広告で、自発的に数百人~数千人レベルのターゲットにアプローチできる場合は、PDCAのチェックの作業はかならず実施すべきです。
ですが、それらの広告手段を利用しない場合、中小企業の集客手段は主にSEOになります。
SEOは効果を発揮するまでに時間がかかりますし、広告のように瞬間的にアクセスを集められる手法とちがって、アクセス数の増減の波もかなり小さいです。
※Googleのアルゴリズム調整や、直近で追加していたページの評価が貯まり、ランク上昇した例などは除きます。
外注を利用しないかぎり中小企業のコンテンツ生産力は少ないので、アクセス解析を緻密・頻繁に実施するメリットが薄い
そしてライティングを外注していないかぎり、中小企業のホームページ担当者のコンテンツ生産量は少ないため、アクセス解析を眺めてもほとんど動きがなく、新たな知見や改善点を見つけられないことが多いのです。
よって中小企業のホームページ運営ではチェックやアクセス解析を密に実施するメリットが薄く、そんな時間があるなら実際に手を動かして文章を書いてページやコンテンツを増やしたほうが集客や売り上げアップに直結しやすいです。
そういった意味で、確認作業や綿密な計画を重視せず、即行動しつづけるOODAループのほうが中小企業のマーケティングには適しているといえます。
よって中小企業のホームページ運営ではチェックやアクセス解析を密に実施するメリットが薄く、そんな時間があるなら実際に手を動かして文章を書いてページやコンテンツを増やしたほうが集客や売り上げアップに直結しやすいです。
そういった意味で、確認作業や綿密な計画を重視せず、即行動しつづけるOODAループのほうが中小企業のマーケティングには適しているといえます。
※ただし、緻密なチェックまでは不要ですが、Webサイトの欠陥は最低限なレベルまでは改善しておいたほうが効率的です。以下の資料を参考にどこを改善すべきかチェックしてみてください。
中小企業のWebマーケティングでのOODAループ
それではWebマーケティングにおいて、どのようにOODAループを実践していくかを見ていきましょう。
主に以下の4つのステップを進めていきます。
【中小企業のWebマーケティングにおけるOODAループの実践方法】
- 観察(Observe)…競合他社・同業他社のホームページの分析
- 状況判断(Orient)…他社のサイトから共通点を見いだして抽象化
- 意思決定(Decide)…どの施策から優先的に実施すべきかの順位付け
- 行動(Act)…ホームページを実際に編集
1.観察(Observe)…競合他社・同業他社のホームページの分析

まずはWeb集客に成功している競合他社・同業他社のホームページをピックアップして、すみずみのページまで熟読してください。
自社が注文住宅メインの工務店であれば、同じく工務店で検索上位を獲得している同業他社のサイトをチェックし、自社がエステや整骨院であれば「○○市 エステ」・「○○駅 整骨院」などの検索キーワードで上位にヒットする同業他社のサイトをチェックしましょう。
また、東京・神奈川・大阪などの都市圏の地名キーワードで上位を獲得している同業他社のサイトはいずれもレベルが高いので、それらも熟読して参考にしてみてください。
競合他社のホームページの分析方法については以下のページで詳しく解説しています。
参考ページ:競合他社のホームページに勝つ方法・対策と、差別化のポイントを解説
自社が注文住宅メインの工務店であれば、同じく工務店で検索上位を獲得している同業他社のサイトをチェックし、自社がエステや整骨院であれば「○○市 エステ」・「○○駅 整骨院」などの検索キーワードで上位にヒットする同業他社のサイトをチェックしましょう。
また、東京・神奈川・大阪などの都市圏の地名キーワードで上位を獲得している同業他社のサイトはいずれもレベルが高いので、それらも熟読して参考にしてみてください。
競合他社のホームページの分析方法については以下のページで詳しく解説しています。
参考ページ:競合他社のホームページに勝つ方法・対策と、差別化のポイントを解説
2.状況判断(Orient)…他社のサイトから共通点を見いだして抽象化

状況判断のステップでは、成功している競合他社・同業他社のホームページを構成している要素を分析し、抽象化の作業を実施します。
競合他社・同業他社の各サイトの具体的な内容から、共通しているポイントを抜き出すのです。
【着目すべき共通点・抽象化のポイント】
- トップページのファーストビュー(ページを開いたときに最初に表示される画面の範囲)に、各社が記載している情報・セールスコピー・写真は何か?
- ヘッダーメニュー(上部メニュー)やサイドメニューにはどんな主要ページが配置されているか?
このようにWebマーケティングでは常に具体的な情報と抽象化した情報を行き来しながら、OODAループを回すことが重要です。
そして、以上の言語化を完了したら各競合他社・同業他社のホームページに掲載されているコンテンツや施策をリストアップしましょう。
そのなかで、自社のホームページに欠落しているコンテンツや施策に着目してください。
それらの要素こそが、競合他社・同業他社との集客力の差を生んでいるギャップに他なりませんから、あとはそこを埋めるような作業を遂行していけばよいだけです。
社内にマーケティングに詳しい人材がいない中小企業でも、実効性のあるプランを自然に作れるのがOODAループの最大のメリットです。
【余談】
なお、ホームページ運営の練度が上がってくると、「この情報はお客さんにとって重要なはずなのに、なぜどこの会社のホームページにもわかりやすく解説されていないんだろう?」と疑問に感じることがしばしば出てきます。
そういった競合他社のホームページに不満を持った点も、かならずコンテンツ化してください。
顧客のニーズをとらえたオリジナルなコンテンツになる可能性が高いので、検索上位を獲得しやすくなります。
3.意思決定(Decide)…どの施策から優先的に実施すべきかの順位付け
コストパフォーマンスが高い施策から優先的に実行していく
前回のOrient(状況判断)で、実行すべき施策のリスト判断が終わったらそのうちのどの施策から順に実行していくかを選択してください。
そこで基準になるのが、施策実行にかかる時間・手間・金銭などのコストが低くて、効果が高い施策から実行することです。
特に重要なのがコンバージョンポイントの整備と、各ページのtitleタグの最適化です。
そこで基準になるのが、施策実行にかかる時間・手間・金銭などのコストが低くて、効果が高い施策から実行することです。
特に重要なのがコンバージョンポイントの整備と、各ページのtitleタグの最適化です。
コンバージョンポイントの改善…「資料請求」・「無料相談」などを追加する
お問い合わせ・資料請求・無料相談などのコンバージョンにいたる場所のことを、コンバージョンポイントと呼びます。
まずは成功している競合他社・同業他社は、どのようなコンバージョンポイントを設定しているかを確認しましょう。
「お問い合わせ」だけでなく、「資料請求」や「見積もり依頼」・「無料相談」なども設置していませんか?
競合他社のホームページを参考に、現サイトに新しいコンバージョンポイントを追加できない検討してみてください。
とくに「資料請求」は獲得できるコンバージョン数が多くなるので設置を急ぎましょう。
各ページのtitleタグの最適化…重要なSEOキーワードを含めたタイトルにする
titleタグとはWebサイトのページタイトルを表す部分のことです。Webページを構成している言語、HTMLのタグの一種です。
titleタグに設定した文字は、ページ中には表示されませんが、GoogleやYahoo!などの検索結果や、Google ChromeなどのWebブラウザの上部に表示されます。
titleタグに設定した文字は、ページ中には表示されませんが、GoogleやYahoo!などの検索結果や、Google ChromeなどのWebブラウザの上部に表示されます。

titleタグはSEO内部対策のタグ設定の中でも、検索エンジンが最も重視している箇所です。
こちらをページごとに最適化するだけで検索順位が大きく変わることも少なくないので、ぜひ試してみてください。
【titleタグ最適化のポイント】
- ページの内容がすぐに分かるタイトルを付ける
- ヒットさせたいSEOキーワードをタイトルに入れる
- ページの内容に関係ないキーワードは入れない
- タイトルはキーワードの羅列ではなく文章にする
- ページごとに固有のタイトルをつける
- タイトルはできるだけ30文字程度に収める
- 重要なSEOキーワードほど前に設置する
- ページタイトルに同じキーワードを何度も入れない
- 階層ごとにキーワードの住み分けをおこなう
4.行動(Act)…ホームページを実際に編集

実際にホームページを編集して行動に移します。
なお、その際に制作会社に依頼しないとページやWebフォームが編集できない状態だと、迅速な改善が望めません。
この場合、CMS(ホームページを簡単に編集・更新できるシステム)を導入して、ホームページをリニューアルできないか検討してみてください。
参考ページ:CMSとは? 意味と種類・ホームページへの導入事例をわかりやすく解説
参考ページ:企業ホームページ(Webサイト)リニューアルのポイントを初心者に解説
なお、その際に制作会社に依頼しないとページやWebフォームが編集できない状態だと、迅速な改善が望めません。
この場合、CMS(ホームページを簡単に編集・更新できるシステム)を導入して、ホームページをリニューアルできないか検討してみてください。
参考ページ:CMSとは? 意味と種類・ホームページへの導入事例をわかりやすく解説
参考ページ:企業ホームページ(Webサイト)リニューアルのポイントを初心者に解説
参考ページ:企業・団体のホームページの開設方法・手順を初心者向けに解説!
なお、コンバージョンポイントの整備やtitleタグの設定などの、短時間で実施できる施策を終了したら、コンテンツの追加・増強などの時間がかかりますが効果が大きい施策に向けて、新たなOODAループを回してみましょう。
集客・アクセスアップに有効なコンテンツとは何かや、作る方法については以下のページをご覧ください。
参考ページ:アクセス数を増やせる、良質なSEOコンテンツの作り方を徹底解説!
参考ページ:Webコンテンツとは何か? 企業ホームぺージのコンテンツ作成を基礎から徹底解説!
参考ページ:ホームページのアクセス数を増やすには? アクセスアップの方法を解説
なお、コンバージョンポイントの整備やtitleタグの設定などの、短時間で実施できる施策を終了したら、コンテンツの追加・増強などの時間がかかりますが効果が大きい施策に向けて、新たなOODAループを回してみましょう。
集客・アクセスアップに有効なコンテンツとは何かや、作る方法については以下のページをご覧ください。
参考ページ:アクセス数を増やせる、良質なSEOコンテンツの作り方を徹底解説!
参考ページ:Webコンテンツとは何か? 企業ホームぺージのコンテンツ作成を基礎から徹底解説!
参考ページ:ホームページのアクセス数を増やすには? アクセスアップの方法を解説
OODAループを活用して、Webマーケティングの成果を最大化しよう!

ここまでOODAループの概要や、PDCAとのちがい、Webマーケティングにおける活用法を紹介してきました。
OODAループはWebマーケティングには最適のフレームワークなので、みなさんもぜひ活用して成果を最大化してください。
なお、弊社では広告費・外注費ゼロ、ホームページ担当者1人でアクセス数を10倍にまで伸ばしたノウハウを以下の資料にまとめています。
OODAループの実践時にも参考になるので、成果を出したい方はぜひ以下から資料を無料ダウンロードしてください。
OODAループはWebマーケティングには最適のフレームワークなので、みなさんもぜひ活用して成果を最大化してください。
なお、弊社では広告費・外注費ゼロ、ホームページ担当者1人でアクセス数を10倍にまで伸ばしたノウハウを以下の資料にまとめています。
OODAループの実践時にも参考になるので、成果を出したい方はぜひ以下から資料を無料ダウンロードしてください。
この記事を書いた人

岡山 幸太郎
株式会社ディーエスブランド Webマーケター
ディーエスブランド入社後、営業を経験したのち自社サイトやお客様サイトのWebディレクションに携わる。現在はSEO(検索エンジン最適化)やコンテンツマーケティングなど、Webにおける集客分野を担当。また、Webセミナー講師としても活動中。